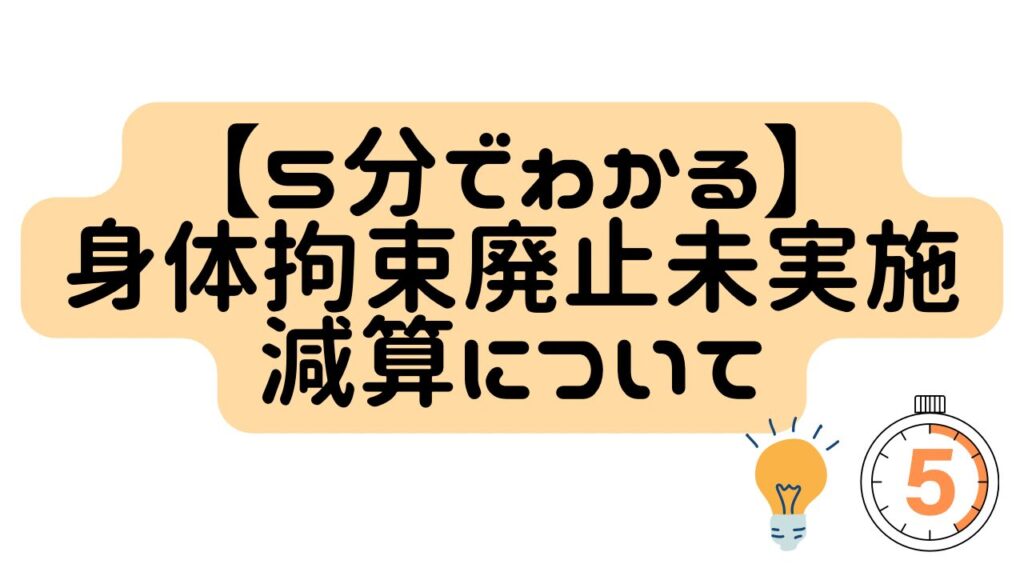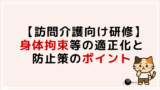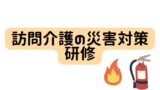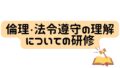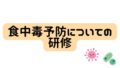※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
近年、障害者への虐待が増加している背景もあり、実地指導でも身体拘束に関する項目はしっかりと確認されています。
身体拘束廃止未実施減算


訪問介護事業所で障害者向けサービスを行うところではR5年4月から身体拘束廃止未実施減算が適用されるから注意が必要だよ
出典 厚労省「令和3年度報酬改定における障害者虐待防止の更なる推進」よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000768753.pdf
減算要件とは?
身体拘束に関する記録が行われていない
身体拘束適正化の委員会が開催されていない(年に1回以上の開催が必要です)
身体拘束に関する指針の整備がされていない
身体拘束に関する研修が実施されていない(年に1回以上の開催が必要です)
※適正に実施されていない事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、利用者全員の単位数から1日につき5単位が減算されます
身体拘束に関する記録
やむを得ず身体拘束を行った場合には拘束した理由や状態、拘束した時間といった情報を記録に残しておかなければならない
身体拘束適正化委員会の開催
身体拘束適正化委員会を1年に1回以上開催する(議事録は必ず作成し保管しておきます)
委員会は事業所単位ではなく、法人単位での設置でOK
委員会に参加する最小人数についての規定はなく、管理者または責任者の参加でOK
ZOOMを活用して委員会を開催することもOK
全職員に向けて委員会で決定した内容を通知する必要がある
身体拘束適正化の指針のポイント
できる限り身体拘束を行わない旨を記載しておく
身体拘束の適正化委員会と研修の開催・頻度を記載しておく
身体拘束が発生した際の報告義務と家族等への連絡方法を記載しておく
指針を作った後は職員だけでなく利用者・家族にも見える位置に貼り出しておく
身体拘束に関する研修
身体拘束に関する研修を1年に1回以上開催する(研修記録は必ず保管しておきます)
「障害者福祉施設における障害者虐待の防止と対応の手引き」より身体拘束に関する考えられる研修の種類の想定として下記の研修等が挙げられています。
「障害者福祉施設における障害者虐待の防止と対応の手引き」https://www.mhlw.go.jp/content/000944498.pdf

この身体拘束に関する考えられる研修は合わせてやっておきましょう
過去の記事から該当するものをリンクさせていますので研修でご利用ください
事務、運転等の業務を担う職員なども対象です。
まとめ
身体拘束廃止未実施減算については内容をしっかり把握し、減算にならないように事前に対策をしておく必要があります。
また、身体拘束をできる限り行わずに支援できるよう、環境整備等を整えておくことが大切です。
※厚生労働省が提供している手引きを研修資料の参考にしてください。https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf