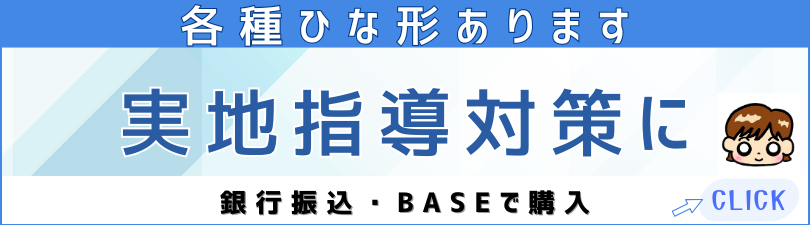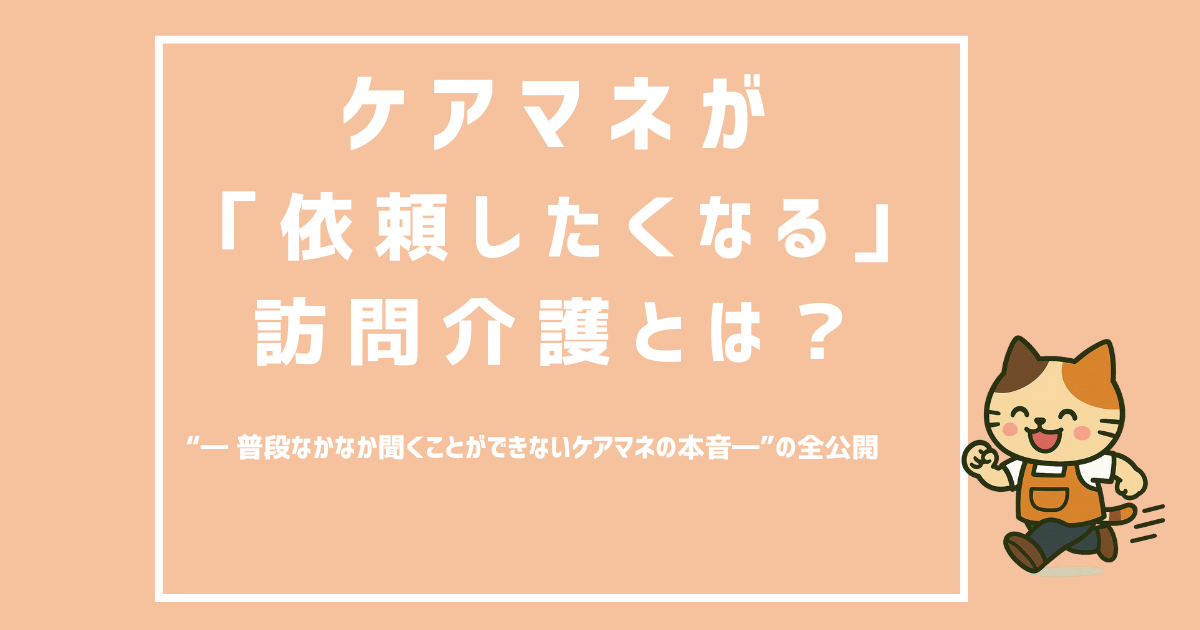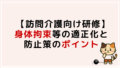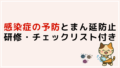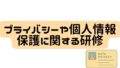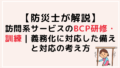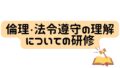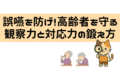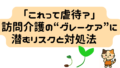有料級情報!“― 普段なかなか聞くことができないケアマネの本音―”の全公開
※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
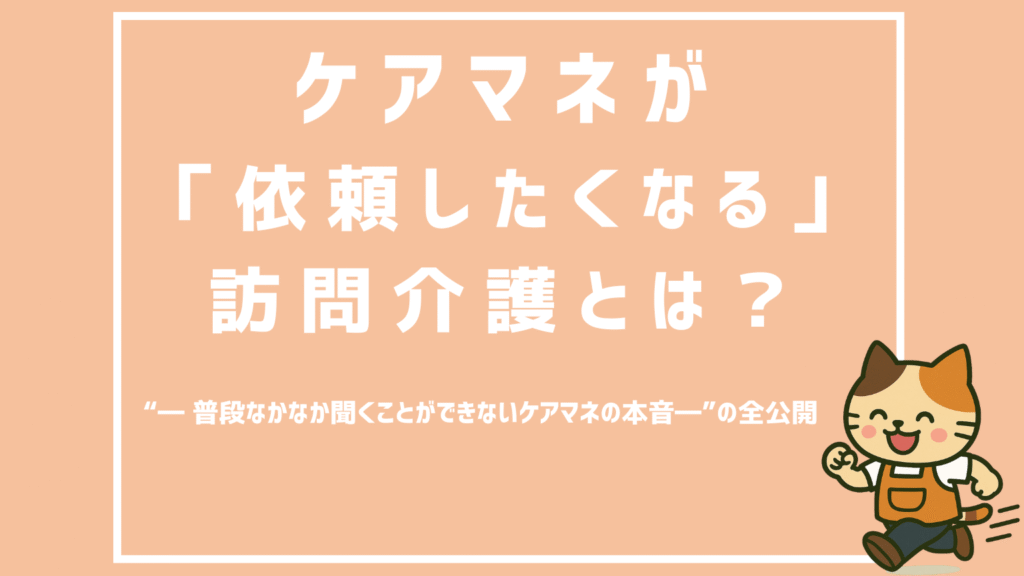
はじめに
・どうしたらもっと利用者さんの紹介が増えるんだろう…
・なかなかケアマネから依頼がこない
・うちには何が足りないんだ?
って、感じたこと一度はありませんか?
今回は、訪問介護事業所の皆さんに、
普段なかなか聞くことができないケアマネの“本音”をお伝えします。
「ここはよく使う」「あそこは…正直あまり使わない」
そんな風に、事業所を選別しているケアマネが多いのが現実です。
じゃあ、どうすれば「またお願いしたい」と思ってもらえるのか?
そして、どうすれば紹介が自然と続く事業所になれるのか?
この記事では、ケアマネの目線で「紹介したくなる訪問介護の特徴」を、本音でお伝えしていきます。
🔽この記事を読んでほしい方
- 利用者数減少で、プレッシャーを感じているサ責
- 事業所を拡大を考えている経営者
- これからサ責を目指す人、サ責としての動きを学びたい新人・中堅スタッフ
- ケアマネとの関係づくりに悩んでいる管理者
結論:依頼される訪問介護事業所の共通点は、“サ責の対応力”

最初に結論をハッキリ言います。
依頼されるかどうかは、サ責さんの対応でほぼ決まります。
どれだけ介護保険制度に詳しくても、
どれだけチラシやSNSが立派でも、
最終的には「このサ責さんだからお願いしたい」と思わせられるかどうか。
それがすべてなんです。
言い換えると、まだまだ人が人を紹介する世界なんですよね。
サービス提供責人者は本当に大変。でも信頼はそこに宿る。
サ責さんの業務が大変なのは、ケアマネも痛い程分かっています。
現場対応・計画書作成・ヘルパー調整・報告業務・クレーム対応…。
「これ一人でやるの!?」ってくらい、負担が大きい。
でも、どんなに忙しくても――

その一言、その対応、ちょっとした気遣いが、ケアマネにはちゃんと届きます。
「あそこの○○さん、対応良かったよ」
「へーそうなんだ~。じゃ新規の人お願いしてみようかな。」
こんな会話がケアマネ事業所の中で自然と生まれ、 依頼ブーストがかかる瞬間があるんです。
ただし、それには“具体的な対応力”が必要。
ここからは、ケアマネが“またお願いしたくなる対応”を解説していきます。
訪問介護の依頼を増やす対応のポイントは4つだけ!!
対応方法は、実はそれほど難しくありません。

忙しい業務の中、営業やコンサルに依頼するような大げさな手間も必要ありません。
下記のポイントを押さえれば間違いなく紹介は増えていきます。
【対応のポイントは4つだけ】
✅契約にならなかった時の対応
✅判断を“投げずに”提案してくれる
✅困難ケースを1件引き受けると紹介は連鎖する
✅柔軟性が“また頼みたくなる理由”になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
契約にならなかった時の対応
訪問介護の現場では、
担当者会議に呼ばれたけど、結局契約にならなかった…
というケース、けっこうあります。
ケアマネ側も実はかなり申し訳なさを感じていて、
「声をかけたのに悪かったかな…」と気にしています。
そんなとき、皆さんはどう対応していますか?
もしここで、サ責さんが、
「こういうのって、あるあるですよね〜。また何かあればぜひ声かけてください!」
と軽く受け流してくれると――
その“神対応”に、ケアマネは心から救われます。
心理学的にも効果あり!返報性の原理とは?
人は、好意や親切を受けると「お返ししたい」と感じる生き物です。

この事業所さん、神対応してくれたから、今度は倍返ししよ。
という心理が自然と働きます。
細かい場面の対応力が、次の紹介に繋がる
大きな営業スキルやテクニックがなくても、
ちょっとした
・気遣い
・笑顔
・言葉のチョイス
こうした日々の対応力が、ケアマネとの信頼関係を作ります。
「契約にならなかった=ムダだった」と思わず、
“次につながるチャンス”として捉えることで、自然と紹介が増えていく土壌ができていきます。
トラブルの判断を“投げずに”提案してくれる
何かトラブルや報告事項があった時に、
「どうしましょう?」とそのまま丸投げされると、ケアマネとして正直しんどいんです。
ケアマネはその現場を見ていないので、正確な判断ができないケースも多い。
「現場判断+提案ベース」の報告ができると信頼につながる
一方で、信頼されるサ責さんの対応はこうなります。
「こういったことがあったので、〇〇の対応をしてみました。ご確認お願いします。」
このように、“現場判断+提案ベース”で報告してもらえるだけで、
「この事業所さんは現場を理解して、きちんと考えて動いているな」と感じますし、
こちらも安心して依頼できます。
▸「救急車を呼ぶ?」「このバイタルは危険?」と迷った時こそ、提案ベースの判断が信頼につながります。
➡ 救急車呼ぶべき?と思ったそのときに|訪問介護のバイタル異常と緊急時現場対応ガイド
▸「ちょっとむせたけど、大丈夫?」
そんな違和感に気づき、先回りして動ける現場対応力こそが、ケアマネからの信頼につながります。
➡ 誤嚥を防げ!高齢者を守る観察力と対応力の鍛え方
ケアマネの業務負担も軽減される
こういった報告の仕方をしてもらえると、ケアマネ側の手間がぐっと減ります。
判断に迷う時間も少なくなり、自分の業務にも集中できて、本当に助かるんです。
ちょっとした言い回しや伝え方ですが、
「丸投げ」ではなく「提案」スタイルで動けるサ責さんは、確実に信頼されます。
困難ケースを1件引き受けると、訪問介護事業所への紹介は連鎖する
次は、ほぼ間違いなく起きる“紹介の流れ”です。
他の事業所が断っているような困難ケースを、
笑顔で「やってみますよ」と言ってくれるだけで
「本当にありがたい…」
という強烈な信頼が生まれます。
その1件の信頼が、2件目・3件目の紹介に連鎖していきます。
柔軟性が“また頼みたくなる理由”になる
ケアマネもなんでもかんでも引き受けてくれと言っているわけではありません。
「それはできません」と制度で線を引くのは大切なことです。
しかし、言い方ひとつで印象は大きく変わります。
「制度的にこれは難しいですが、こういうやり方なら可能です」
そんな風に“できる方向”で寄せてくれる姿勢。
それがあるだけで、ケアマネ側の印象はガラッと変わります。
ケアマネが求めているのは「なんでも屋」ではなく
「一緒に考えてくれる存在」を求めているんです。
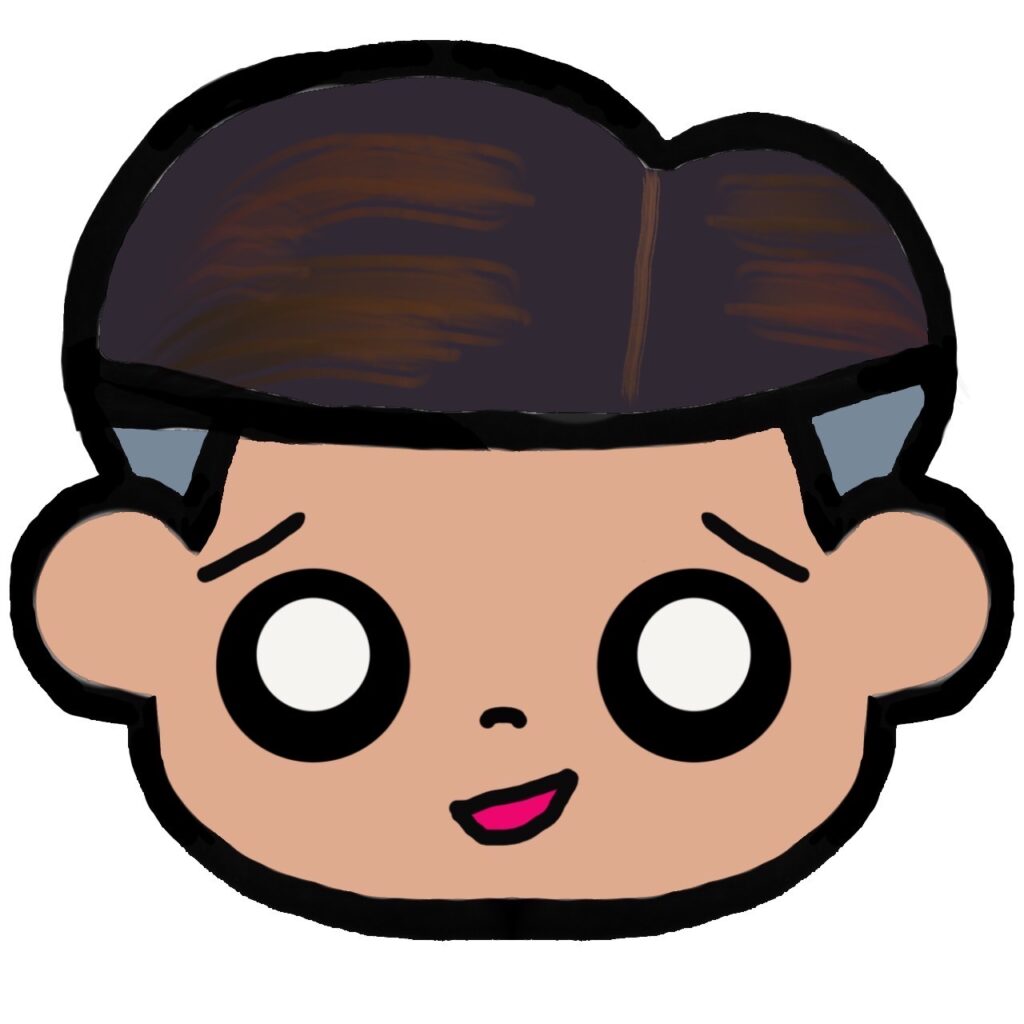
実は孤独なんですよ、ケアマネって…
一緒に考えてほしいのが本音。
派手な営業より“静かな仕組み”が効く
ケアマネもサ責さん同様に基本、かなり忙しいです。
営業訪問をされても、ちょっと迷惑な時もあるんです。
でも、
- 必要な情報が揃っているホームページ
- 様子が伝わるブログや通信
- 一目で伝わるFAX資料
こういった「静かな情報発信」が、じわじわ効いてきます。

上記の三つは、こちらの時間に余裕があるときに見れるので、助かります。
ケアマネを“自然に誘導する仕組み”をつくる
たとえば、サービス申込時にサ責さんが
「申し込み書はホームページにございますので、そちらからダウンロードしてお使いください」
と伝えるだけで、ケアマネは自然と事業所のホームページにアクセスします。
その時、ホームページに対応エリアや職員体制、柔軟な対応などが分かりやすく載っていれば、
ただの申し込み手続きが、“事業所の魅力が伝わるきっかけ”になるんです。
つまり、ケアマネに「売り込む」押す営業ではなく、
“来てもらう導線”をつくる=引きの営業のほうが、はるかに効果的。

ほとんどの訪問介護事業所は押しの営業を行っているから気を付けてください。
※引きの営業…顧客に「欲しい」と思わせ、自発的に問い合わせや購入をしてもらう仕組みの営業。
- コンサルやWEB業界でも「引き寄せ型営業」として普通に使われている概念
≪特徴≫
- ゴリ押ししない
- 信頼や興味を“引き出す”ように設計されている
≪具体例≫
- ブログやSNSで役立つ情報を発信し、そこから商品やサービスに関心を持ってもらう
- 問い合わせや申し込みを「相手から」してもらえるよう導線設計する
≪対義語:押す営業≫
- テレアポ、飛び込み営業など、「自分からガンガンアプローチして売るスタイル」
※導線設計も含めたホームページづくりを希望される場合は、こちらで訪問介護専門の制作も対応しています。
おわりに:紹介は、信頼の上に成り立つ
ここまでお伝えしてきた内容は、すべて現場でのリアルな体感です。
もちろん制度も大事、仕組みも大切。
でも最終的には、
「またお願いしたい」と思える人がいるかどうか。
それが紹介につながるすべての源だと思っています。
4つの対応すべて行えれば完璧ですが、ちょっとハードルが高いな思われる場合は、どれかできそうな
1つでも行ってみてください。
長期的にみて必ず効果が出ると思います。
【関連記事】
現場の声から生まれた研修記事・スタッフ育成のヒントはこちら
→ 今すぐ使える!訪問介護のヒント集はこちら|ケアパワーラボ
✅【PR】各種書類ひな形一覧