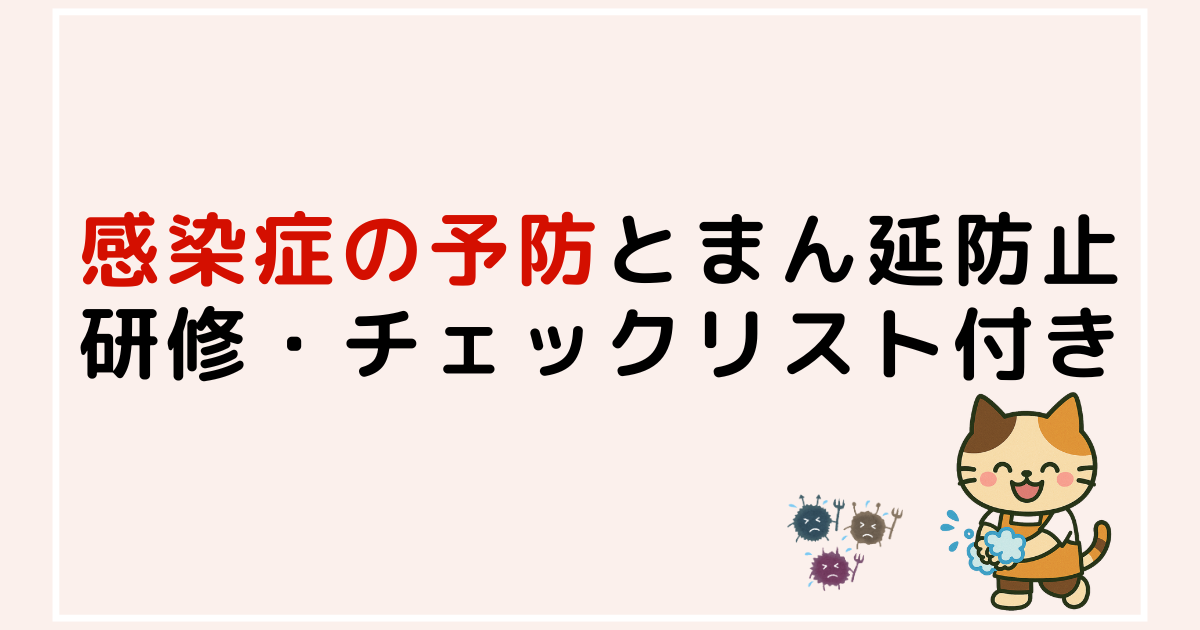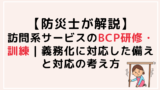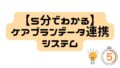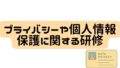※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷
✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる
✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫
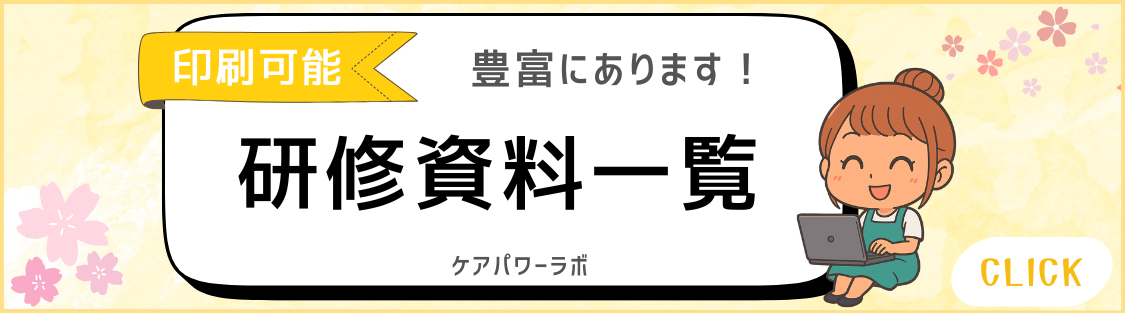
参考資料:【厚生労働省感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等】
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_houmon-2_s.pdf
訪問介護の現場で気をつけたい「感染症」とは?
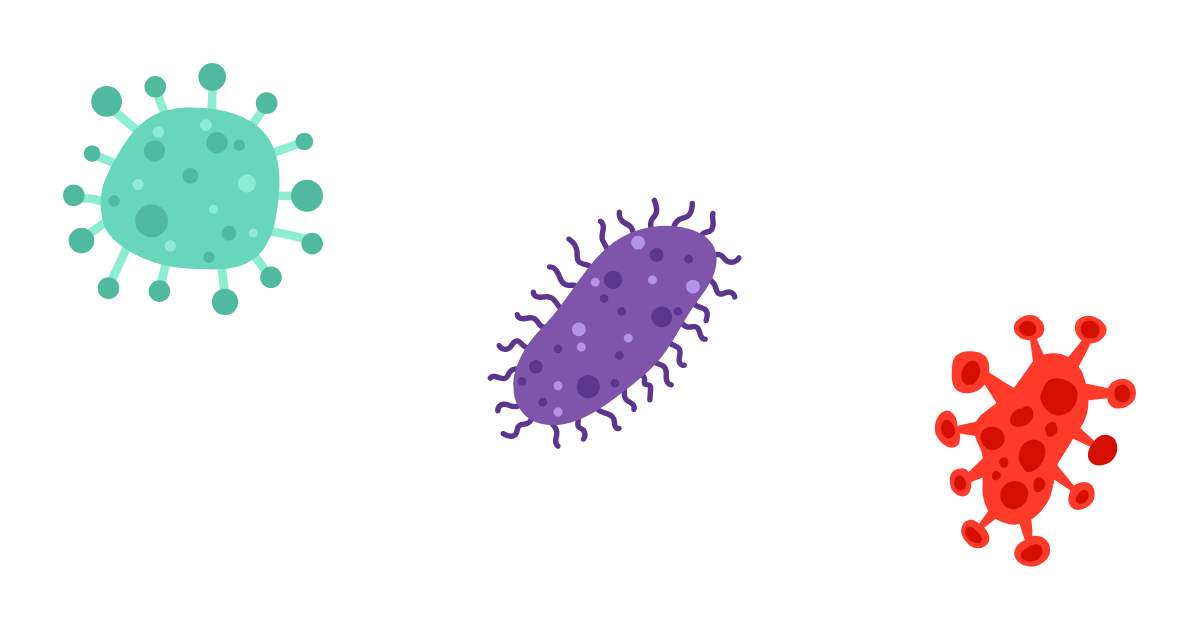
訪問介護の仕事では、体調を崩しやすい高齢者や障がいのある方の自宅を訪問します。
そのため、感染症を防ぐことが非常に重要となります。
利用者だけでなく自分を守るために、まずは感染症・対策について正しく理解をしましょう。
(出典:厚生労働省「感染症の予防及びまん延防止に関する研修資料」 https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf)
感染症とは?
感染症とは、ウイルス・細菌・カビなどが体の中に入って起こる病気のことです。
熱・咳・嘔吐・下痢などの症状が見られることがあります。
▼ 代表的な感染症:
- インフルエンザ
- ノロウイルス
- 新型コロナウイルス
高齢者や障がいのある方にとっては、重症化のリスクが高いため注意が必要です。
感染症が成立する3つの要因
感染症は「感染源」「感染経路」「感染を受ける人」の3つが揃うと成立します。
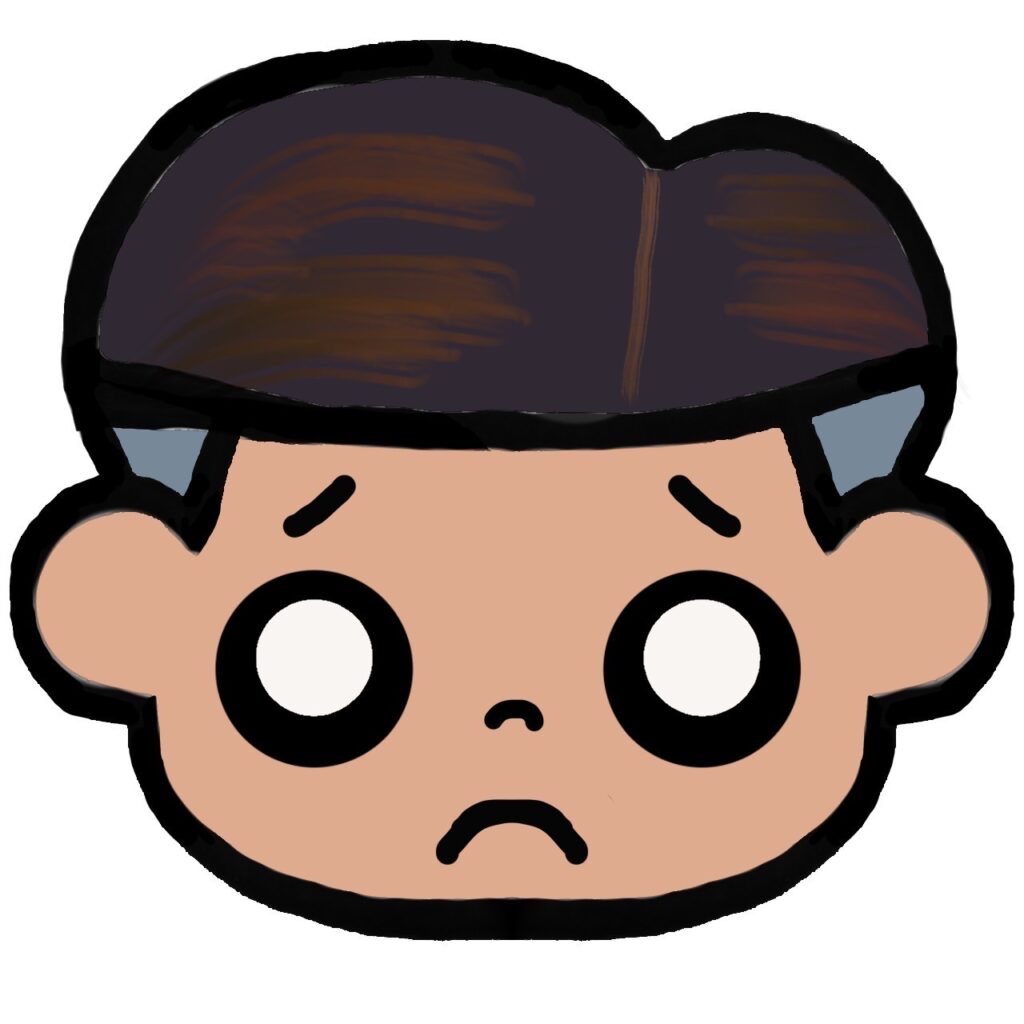
感染症は火事とよく似ているんだ。
感染症は火事と似ている。三要素比較表
| 火災の三要素 | 感染症の三要素 | 説明(共通点) |
|---|---|---|
| 火(点火源) | 感染源 | ウイルス・菌など、「発生源」「元になるもの」 |
| 酸素(助燃物) | 感染経路 | 「通る道」があると広がりやすい |
| 可燃物(燃える物) | 感染を受ける人(宿主) | 免疫が弱い人がいると感染しやすい |

感染予防の3原則
- 火を防ぐには:点火源・助燃物・可燃物のどれかを断つ。
- 感染を防ぐには:感染源・感染経路・感染しやすい状態を断つ。

特に介護サービスでは感染源と感染経路を断つ事が重要なんだ。
高齢者は免疫が弱い=感染を受けやすい人が多いため、
- 感染源を断つ(病原体を持ち込まない・早期発見・隔離・消毒)
- 感染経路を断つ(手指衛生・マスク・タオルや食器などの共用を避ける)
この2つが感染対策の柱になります。
利用者の免疫を強くすることも大切ですが、私たちは即効性のある「感染源」「感染経路」の遮断が最優先となります。
感染源と感染経路
感染源とは
病気のもとになる菌やウイルスがいる場所や物のことです。人、動物、環境(空気、水、物品など)も感染源になる場合があります。
▼ 主に感染源になる可能性があるもの。
| 感染源の種類 | 補足 |
|---|---|
| ① 嘔吐物、便、粘膜 | ノロウイルス、大腸菌などが含まれることがある |
| ② 体液・血液痰などの分泌物 | B型肝炎ウイルスなどの感染源となる |
| ③ 使用済みの注射針など | 再使用や不適切な処理によって感染の恐れあり |
| ④ 汚染された手指・手袋など | 病原体の媒介者となり得るため「手の管理」が重要 |
感染経路(感染ルート)
感染経路(感染ルート) を通じて体内に病原体が入ることで感染します。
▼ 感染経路(感染ルート)は大きく3つ。
- 接触感染
ドアノブなどに付着した菌が、手を通して口や目に入ること。 - 飛沫感染
くしゃみや咳などの飛沫を吸い込んで移ること。 - 空気感染
ウイルスが空気中を漂い、それを吸い込むことで移ること。
現場でよくある例
🔻 くしゃみが飛んでドアノブにかかり、そのドアノブを素手で触る。
➔接触感染のリスク。
🔻 マスクを顎へずらしたままケアをし、利用者のくしゃみが顔にかかる。
➔飛沫感染のリスク。
🔻 感染が疑われる利用者に対して、換気をせずにケアを開始。
➔空気感染のリスク。
感染源と感染経路を断つ・現場での対策ポイント
- 手洗い・手指消毒の徹底。
- マスク、手袋などの適切な使用。
- こまめな換気をしっかり行う。
- 使い捨てのものは廃棄する。
| 対策 | 感染源を断つ | 感染経路を断つ |
|---|---|---|
| 手洗い・手指消毒の徹底 | 病原体を除去し、自分を感染源にしない | 手を介して他人や物に病原体を広げない |
| マスク、手袋などの適切な使用 | 咳・くしゃみで病原体を飛ばさない | 飛沫や接触を物理的に遮断する |
| こまめな換気をしっかり行う | ― | 空気中の病原体濃度を下げ、空気感染を防ぐ |
| 使い捨てのものは廃棄する | 汚染物を現場から排除する | 汚染物を介した接触経路を遮断する |
- 感染の原因は「接触・飛沫・空気」
- 手洗い、マスク、換気でリスクを大幅カット。
※換気を行う場合、風の流れができるよう、2方向の窓を、1時間に2回以上、数分間程度、全開にしましょう。
(出典:厚生労働省「感染症の予防及びまん延防止に関する研修資料」 https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf)
✅厚労省が出している『感染対策普及リーフレット』写真つきで正しい手洗い・手指消毒がわかりやすく学べます。➤(厚生労働省)感染対策普及リーフレット
現場で使える!感染予防の消毒液
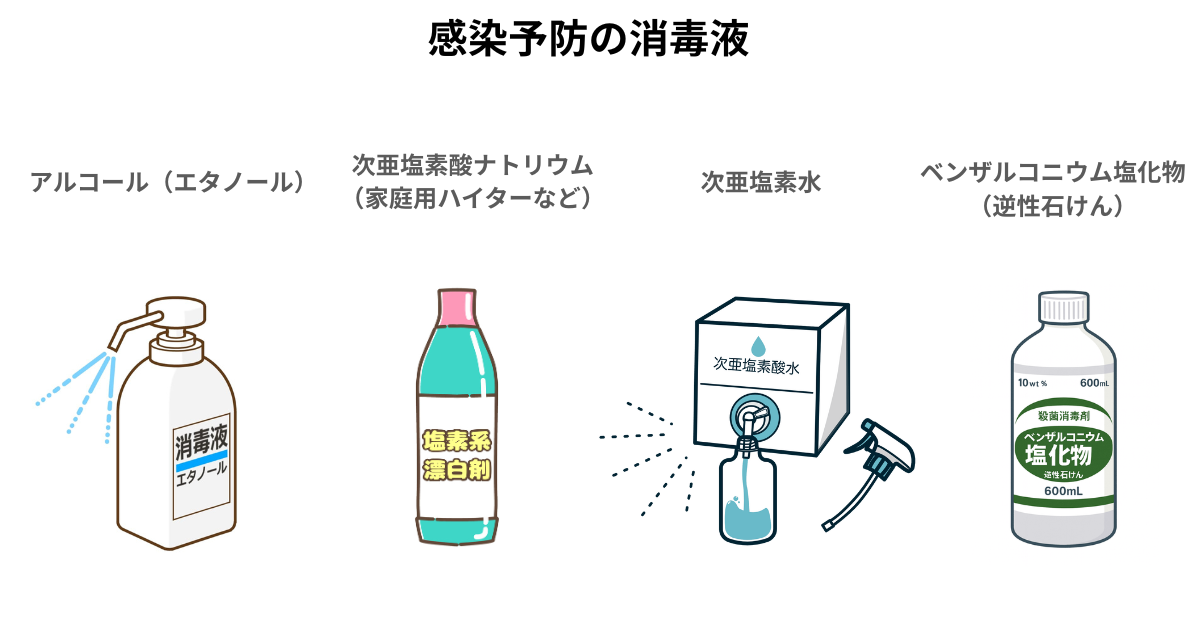
| 消毒液名 | よく使う場面 | 濃度の目安 | 注意点 |
| アルコール(エタノール) | 手、ドアノブ、スマホなど | 70〜95%のものを使用(市販品はそのまま使用) | 火気厳禁・手荒れ注意 |
| 次亜塩素酸ナトリウム(家庭用ハイターなど) | 嘔吐物、血液処理 | 水500ml+ハイター小さじ1杯(5ml)=約0.05% | 金属・肌に不向き |
| 次亜塩素水(弱酸性) | 室内空間、ドアノブなど | 市販品はラベルに書かれた濃度のまま使用(例:50ppmの製品は薄めずそのまま使う) | 光・熱で効果低下・長く保存できない・手指にも使える |
| ベンザルコニウム塩化物(逆性石けん) ※市販のうがい薬や洗剤にも使われる成分です | 器具の消毒、手洗い補助 | 水1L+原液小さじ2杯(10ml)=約0.1% | 他の洗剤と混ぜない すすぎ必要 |
- 嘔吐物→ハイター0.05%
- 日常の拭き掃除→アルコール70%以上
- 金属→アルコールでOK、ハイターはNG
✅ 関連記事:食中毒予防の研修資料もご活用ください
食中毒は感染症と同じく、現場での「持ち込まない・拡げない」意識が重要です。
➤ 食中毒予防についての研修資料はこちら(PDF印刷対応)
Q&Aで確認しよう
- Q嘔吐物を処理するとき、どの消毒液を使えばいい?
- A
次亜塩素酸ナトリウム(家庭用ハイターなど)を0.05%に薄めて使います。ペーパータオルなどで拭き取った後は、二重袋で廃棄します。
- Qスマホやドアノブを毎日拭くのに向いている消毒液は?
- A
アルコール(エタノール)がおすすめです。70%以上の濃度が効果的です。
- Qベッドの柵やリモコンなど、金属部分の消毒は?
- A
アルコール(エタノール)が◎。次亜塩素酸ナトリウム(ハイター)は強力な殺菌力がありますが、サビの原因になるので要注意。
- Q「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」、名前が似ていますが同じものですか?
- A
いいえ、成分や性質が違います。
次亜塩素酸ナトリウム
→ 漂白剤(ハイターなど)に使われ、希釈すると消毒液になります。刺激が強く、金属腐食や皮膚・衣類へのダメージがあるため、使い方に注意が必要です。
次亜塩素酸水
→ 食品や手指の除菌にも使われることがあり、刺激が少ないのが特徴。ただし、有効塩素が時間とともに減りやすく、長時間の保存には向きません。
- Q逆性石けんって何ですか?
- A
殺菌・消毒を目的とした化学物質で、普通の石けんとは性質が逆です。
普通の石けん(石けん・ボディソープ)
→ 陰イオン性で、皮脂や汚れを洗い流すことが目的。
逆性石けん
→ 陽イオン性で、細胞膜を壊して殺菌・消毒する。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html)
訪問の際の嘔吐の処理方法を学んでおきましょう。下記の動画が参考になります。
✅参考動画:高崎市「感染症予防 ~嘔吐物処理方法~」(2018年10月)
毎日の感染予防チェックリスト【自分を守る行動】
訪問介護では、自分自身を守ることが結果的に利用者を守ることにも繋がります。
日々のルーティンの中に感染予防のチェックを組み込んでおきましょう。
出勤前のチェックリスト
◻︎咳・喉の痛みは?
→軽い症状でも他の人にとっては重大な感染源となります。体調を正しく把握するためにバイタルチェックを行います。
◻︎熱はないか?
→多くの感染症は発熱から始まるため、熱がある状態で無理に出勤すると、利用者や職場の仲間へ感染を広げる危険があります。
移動中・事業所内での注意
◻︎電車やバスの吊り革に触れた後は手指消毒
→不特定多数が触れる箇所はウイルスが付着しやすいため、触れた後は必ず手洗いや手指消毒を行います。ウイルスを持ち込まない意識が大切です。
◻︎手洗い・手指消毒はこまめに行う
→「外から自宅に入ったとき」「物を触ったあと」「食事前」など、タイミングを意識することが大切です。
◻︎マスクは鼻まで覆う。顎にずらすのはNG。
→正しくつけないと効果が減ります。鼻を出している・顎にずらして再装着することで、マスク表面に触れて逆に感染リスクが高まります。
必要性の背景を理解することで、「なんとなくやる」から「意味を持って実践する」行動に繋がります。
現場の安全は、こうしたひと手間の積み重ねで守られます。
(出典:厚生労働省「感染症の予防及びまん延防止に関する研修資料」 https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf)
Q&Aで確認しよう
- Q自分の家族が風邪気味でも、自分に症状がなければ出勤していい?
- A
無症状でも感染の可能性はゼロではありません。出勤前に必ず管理者へ連絡し、指示を受けてください。 感染拡大防止のため、状況によっては自宅待機となる場合があります。
- Q利用者の咳がいつもよりひどいけど、熱はない。どうすれば良いですか?
- A
咳が強くなっている場合は、感染の可能性もあるため、マスク着用・バイタルの確認・換気強化などを行いつつ、様子を具体的に記録しすぐに管理者へ報告します。管理者は家族やキーパーソンに報告・受診の促しをします。
- Q出勤前に体温を測るのを忘れた場合は?
- A
出勤前に体温を測り忘れた場合は、事業所で速やかに計測し、記録に残してから業務に入りましょう。
利用者宅での感染対策【現場の動きに沿って】
実際の感染対策では「頭では分かっていても、動きの中で忘れる」ことがあります。
だからこそ、一連の流れとして身につけることが大切です。
玄関での感染対策
◻︎上着などの必要ないものは室内に持ち込まない。
◻︎入室前に必ず手指消毒を行う。
入室後の感染対策
◻︎ケア前にもう一度手洗いをする。
◻︎必要に応じてエプロン・マスク・手袋を装着する。
ケア中の感染対策
◻︎利用者に顔を近づけすぎず、距離を保つ。
◻︎排泄物、嘔吐物の処理時は手袋・エプロンを必ず装着する。
退出時の感染対策
◻︎汚れた物は事業所のルールに従い適切に処理。
◻︎最後にしっかり手指消毒を行う。
- 手袋をしたままバッグを触ってしまい、ウイルスを自宅に持ち帰ってしまった。
- 嘔吐物処理時にエプロンをせず、制服が汚染されてしまった。

感染対策は「習慣づけ」が大切なんだ。また、どんなに急いでいても、感染対策を怠らないようにしていこうね。
▼ 感染対策3つのポイント
| 原則 | 具体的な行動例 |
|---|---|
| 持ち込まない | ・出勤前の体調チェック・手指消毒やマスク着用 |
| 持ち出さない | ・外出時のマスク継続使用など |
| 拡げない | ・手洗い・手指消毒の徹底・咳エチケットの徹底 |
(出典:厚生労働省「感染対策マニュアル(訪問系)」https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_houmon-2_s.pdf)
標準予防策(スタンダード・プリコーション)
標準予防策(スタンダード・プリコーション)とは?
すべての利用者を「感染している可能性がある」と想定し、誰に対しても・いつでも・同じように感染対策を行うという考え方です。
これは、「症状がある人だけ注意する」ではなく、無症状でも感染のリスクがあるという前提で、日常的に手袋・マスク・手指衛生などを徹底することを意味します。
症状がなくても感染している場合があるため、例外なく予防を徹底する必要があります。
基本3点セット
| 対策内容 | 目的 | 使用例 |
| 手洗い・手指消毒 | 菌やウイルスを洗い流す | 入室前後・ケア前後・トイレ後など |
| 個人防護具の使用 | 感染物に触れないようにするため | 手袋・マスク・エプロンなど |
| 咳エチケットの実践 | 飛沫による感染を防ぐため | 咳が出る時はマスクやティッシュ使用など |
個人防護具の装着・脱着手順
【装着時】
- 手を洗う/手指消毒
- エプロン(またはガウン)を着用
- マスクを装着
- 手袋を装着(※最も汚れるため最後)
【脱着時】
- 手袋を外す(※最も汚れているので最初に)
- エプロンを脱ぐ
- マスクを外す(※紐を持って外す)
- 最後に必ず手指消毒を行う
(出典:厚生労働省「介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き第3版 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf)
✅参考動画:厚生労働省 「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策(YouTube)」
➤感染対策「個人防護具の装着・脱着」について非常にわかりやすく解説されています。この研修で一緒に学んでおきましょう。
記録の重要性と具体例
記録は「後から見て何が起きていたか」がわかるように書くことが大切です。
特に感染に関わる記録では、小さな変化を具体的に残すこと。
感染を防ぐ記録のコツ
- いつ・どこで・何があったか、できるだけ具体的に書く。
- 利用者が話した言葉は「そのまま」記録する。
- 客観的な事実(数字・様子・行動)をセットで書く。
良い記録と悪い記録の比較例
状況
15時、普段ならプリンを完食する利用者が半分しか食べず、
「なんか寒い気がする」と言った。手が冷たく、軽く震えている。体温を測ると38.0℃。
食欲がなく寒そうにしていた為、毛布を掛けた。
- 「食欲なし」だけ → 何があったか具体性なし
- 「寒そうだった」だけ → 証拠(数値や本人の言葉)がない
15時ごろ、おやつのプリンを半分残し、「なんか寒い気がする」との訴えあり。
手が冷たく震えがあり、体温38.0℃。管理者へ報告し、安静にしてもらった。
✅ 関連記事:BCPには感染症対応も含まれます。
防災士が解説!災害と感染症、両方に強い職場づくりへ。
➤ 訪問介護のBCP研修・訓練資料はこちら(PDF印刷対応)
なぜ感染予防で記録が大事なのか
- 早期発見につながる
→ 小さな体調変化を他の職員がすぐに把握し、受診や隔離などの対応が取れる。 - 感染拡大を防げる
→ 発熱や症状の始まりを明確に残すことで、濃厚接触者の特定や対応が迅速になる。 - 証拠として残る
→ 後から「いつ、何があったか」を第三者が確認でき、対応の妥当性を証明できる。
つまり記録は、『現場のバトン』であり、『感染予防の第一歩』となります。


ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
✅ できていますか?R6年から義務化された感染症対策。
指針作成、委員会開催、研修・訓練の実施記録が未対応だと減算対象です。
➤こちらでチェック|ケアパワーラボ
✅ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」
→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/
まとめ
訪問介護の現場では、様々な利用者と向き合います。
元気そうに見えても、体の中では感染症と闘っている方もいれば、ほんの少しのウイルスで命に関わる方もいます。
「うつさない」「うつらない」ために、特別なことをする必要はありません。
大事なのは、日々の当たり前を、丁寧に積み重ねること。
手洗いをする・消毒液を使う・気になることがあったらすぐに報告をする。
当たり前のようで、ついおろそかになりがちなことを、「今日からまた意識しよう」と思えることが、感染を防ぐ第一歩です。
もし迷ったら、一人で判断せず、誰かに相談してください。
誰かの体を守ることは、まわり回って自分自身を守ることにも繋がります。
介護の現場は、「人と人」が向き合う場所。
安心できるケアは、安心できる環境から。
あなたの行動が、その土台を作っていきます。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

本資料は、介護の現場での共有・活用を目的として作成しています。 以下のようなご利用はご自由にどうぞ:
・印刷して使用
・職場内での回覧・配布
・個人での保存・参照
ご遠慮いただきたいご利用
以下の用途でのご使用はお控えください:
・無断転載(Webサイト・SNS等への投稿など)
・無断での再配布・再編集(PDF配布、内容の加工などを含む)
・商用利用(有料教材・商品の一部としての使用など)
文章・図表などの無断引用(出典・文脈の明示がないままの一部使用など)
外部でのご紹介・引用について
外部メディア・資料・SNS等で当資料の一部を引用・掲載される場合は、 必ず以下のように出典を明記してください:
※文脈を歪める形での引用や、誤解を招く編集はご遠慮ください。 不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください: info@care-power-lab.com
★リンク・ご紹介は大歓迎です!
皆さまのつながりが、介護現場の力になります。
感染予防のためのチェックリスト
□ 睡眠と食事を十分にとっていますか?
□ 手洗いをこまめにしていますか?
□ 他人が触れた場所をさわった手で、顔や髪をさわっていませんか?
□ 体温測定をしていますか?
□ 風邪の症状(発熱、咳、鼻水、のどの痛み等)はありませんか?
□ 息苦しい、強いだるさ、味覚や嗅覚の異常はありませんか?
□ 同居の家族にそのような症状はありませんか?
これらの症状がある場合には、無理をせず、出勤する前に管理者に連絡、相談して下さい。
□ 出入りの際、食事の前に、手洗いと手指消毒をしていますか?
□ マスクを正しくつけていますか?
□ 定期的に室内を換気していますか?
□ 複数の人が触る場所を定期的に消毒していますか?
□ マスクを正しくつけていますか?
□ 支援に必要ない物(上着など)は、玄関に置いていますか?
□ 介助前に、手洗いと手指消毒をしていますか?
□ 居室の換気をしていますか?
□ 汚染された物をさわる時には、使い捨ての手袋やエプロンをつけていますか?
□ 利用者の体温を確認しましたか?
□ 風邪の症状や息苦しさや強いだるさ、味覚や嗅覚異常の訴えはありませんか?
□ 同居や立ち合いの家族にもこれらの症状はありませんか?
これらの症状がある時は、すぐ管理者に報告して下さい。
□ 無意識にマスクや顔、髪をさわっていませんか?
□ 自分の顔を利用者の顔を前にもっていっていませんか?
□ 訪問記録を書く時に、手洗いと手指消毒して手(ペン)で書いていますか?
本記事はPDFとして印刷できます
【訪問介護研修】感染症の予防とまん延防止研修|現場で使える実践対策とチェックリスト(研修資料として使えます)
整えたレイアウトでそのまま印刷OK
研修・ミーティング・配布用にご活用ください。
研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン
アンケートの実施
記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。
ブログの質の向上に役立てさせていただきます。
アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩
- 厚生労働省「訪問系サービスにおける感染防止対策マニュアル(第2版)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_houmon-2_s.pdf
- 厚生労働省「介護現場における(訪問系サービスなど)感染対策の手引き第3版」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
- 厚生労働省「感染症対策の基本」 https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf