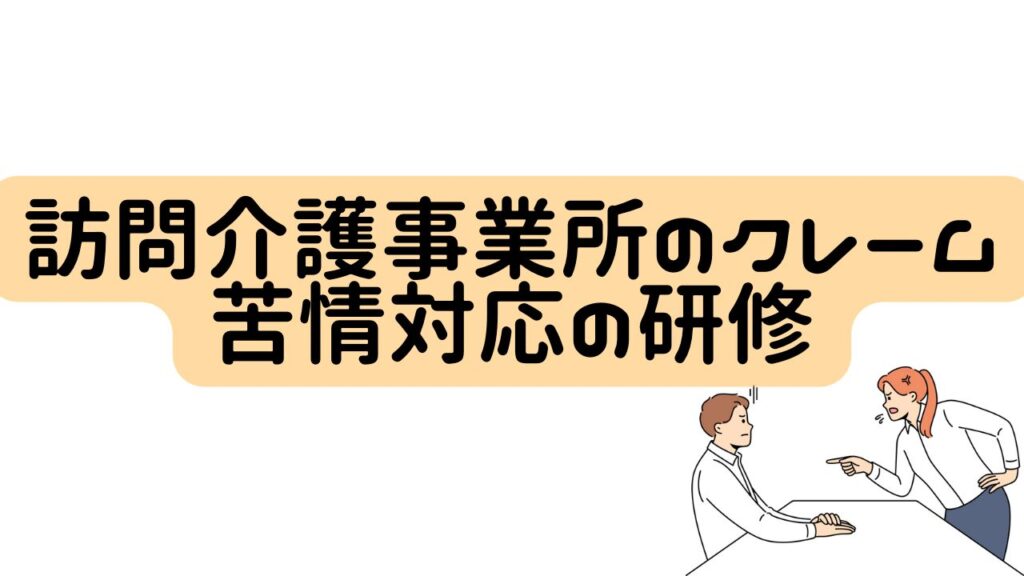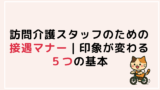※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷
✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる
✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

はじめに

クレームの対応って大変よね…。
クレーム・苦情対応は、サービスの質を向上させ、利用者の満足度を高めるために重要な役割を果たします。
適切な対応を行うためには、その必要性を理解し、具体的な対応方法を知ることが求められます。
クレーム・苦情対応の必要性
訪問介護事業所に対するクレームや苦情は、利用者やその家族からの貴重なフィードバックです。
それらは、サービスの問題点や改善すべき点を指摘してくれるため、事業所として積極的に受け入れていきましょう。

適切に対応することで、利用者との信頼関係を築き、サービスの質を向上させることができます。
苦情相談窓口の設置など
事業所は利用者が相談しやすい窓口の設置・連絡体制やその手順を整えなければなりません。
・窓口を設置し担当者を決める
・職員間の連絡体制や手順を決める

上記は契約書や重要事項説明書にあらかじめ記載し、利用者等に説明をしなければならないんだよ。
具体的な対応方法
傾聴
クレーム対応での「傾聴」とは、意見や不満を、ただ聞くだけでなく、その背景にある感情やニーズを理解しようとする態度を指します。
感情面も含めて自分の事を理解されると、安心感が生まれ、気持ちが静まります。

話をただ聞いていればいいわけではないのね…。
時間をかけて聞く: 相手の話す時間をしっかりと確保し、途中で遮らず、最後まで話を聞くことが大切です。
反応を示す: うなずきやあいづちといった反応を示すことで、ご家族や本人が話を進めやすくなります。
感情を理解する:話をしっかりと聞きながら相手の感情に理解を示します。
ニーズを把握する:相手が何を訴えていて、何を求めているのか正しく把握していきます。

このほかにも話を聞く時の表情や態度・服装なんかも重要となるんだよ。接遇の研修で細かく記載してあるので参考にしてね。
部分謝罪

部分謝罪??
事実確認がない状態での全面的な謝罪は、非を認めた事になりかねません。
その為、相手の感情という部分に対して『不快な思いをさせて、申し訳ございません』と部分的に謝罪を行うようにします。

嫌な思いをさせてしまった事は事実だもんね…。
事実確認を行う
相手が何を訴えているのか理解できたら、次は事実確認を行います。
小さな事でも必要な事はすべて記録する事が重要です。
・どんな事が起こったのか。
・どのような不満をもっているか。
・どうしてほしいと考えているのかなど。
また、クレームの対象がヘルパーであった際にはヘルパーからも聞き取りを行います。

ここで気を付けなければならない事は、対象のヘルパーが悪いと決めつけないようにしよう。
慎重に事実確認を行っていく事が重要です。
解決策を提示する
事実確認を行った後は、対応策を検討し、できる限り早急に解決策を提示するようにします。
この度は、弊社のミスによりお手数と不快な思いをおかけしてしまったことを深くお詫びいたします。今回の件に対し〜(解決策を提示)

相手がどうしてほしいと考えているのかを聞き取り、総合的に判断し解決策を提示しないといけないのね。
クレームに対し再発防止の対応より、まず問題解決の対応を優先していきます。
NG行為
クレーム対応をする際にNG行為があります。
反論する:相手に強い言葉で言われると、つい反論したくなる気持ちもわかりますが、傾聴を意識し聞き取りに集中していきましょう。
身内をかばってしまう:『担当の○○も忙しかったのだと思います。』と身内をかばう発言をしてしまうと、相手に不信感を与えてしまいます。
待たせてしまう:クレーム対応ではスピード感が大事と言われています。待たせる事で放置されていると印象を持たれてしまう為、相手の負の感情は増大していきます。
話を遮る(さえぎる):話を遮ることで相手は不満を吐き出せず、冷静になれなくなってしまいます。傾聴を意識し、一通り話を聞く姿勢をとる事が重要です。
再発防止策の検討
クレーム対応が終わったら、内容を記録に残す必要があります。
事実確認の際に行った記録もここでまとめていきます。
クレームの内容や対応経過を記録する事で職員同士で共有ができるようになり、また、まとめておくことで再発防止の検討や問題の明確化に活用しやすくなります。
・起こった順番に客観的事実のみを記載する。
・職員の負担にならないように簡潔な様式にする。
・記録をサービスの向上につなげる。

客観的事実か~。
記録する時に憶測とか,感情をいれないようにしないとねー。
クレーム・苦情の具体的な事例
訪問介護事業所でよくあるクレーム・苦情の事例としては、以下のようなものがあります。
掃除中に物を壊してしまった。
訪問時間に無断で遅刻する。
滞在訪問を早めに切り上げてしまう。
食器の汚れが落ちていない。
臭いがするゴミを放置したまま帰った。
頼み事をしたが聞いてもらえなかった。
身だしなみが悪い。

上記は本人・家族からケアマネによくある相談・苦情の事例だよ。

忙しい時に起こりやすいものばかりね。
人が少ない中大変だけど、時間と心に余裕をもたないとね…。
【PR】ホームページ制作サービスのご案内
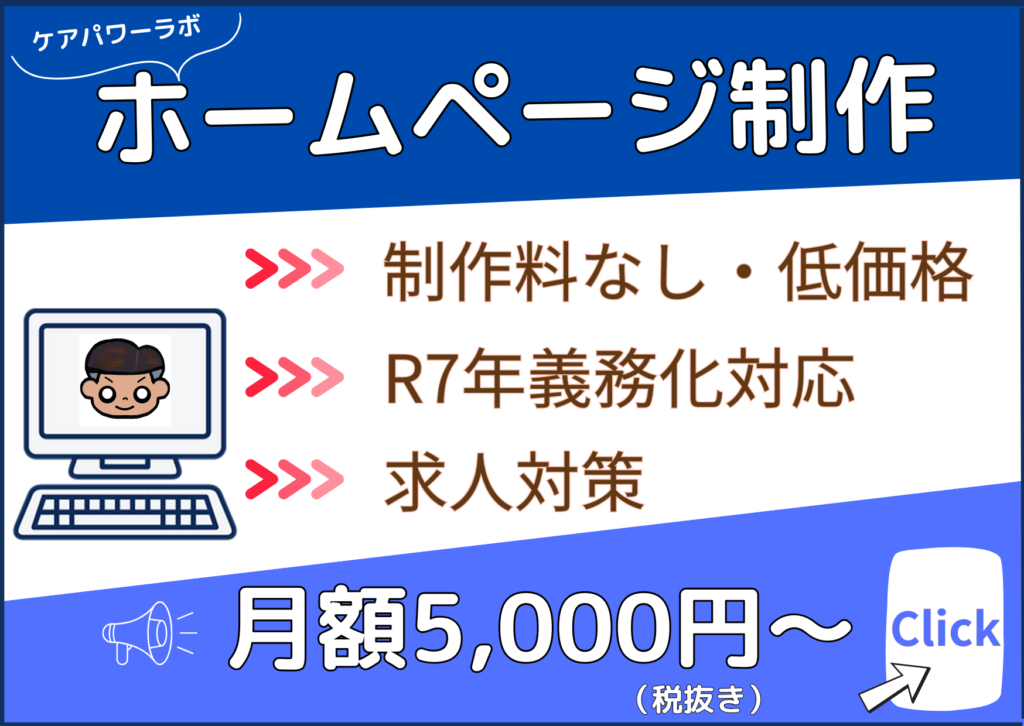
カスタマーハラスメントに対して
カスタマーハラスメントとは、利用者やその家族等から職員・事業所に対して理不尽なクレームや、介護サービスの範囲を超える過剰な要求・脅迫などの不当な行為のことです。

利用者やその家族からの要求に妥当性があっても、その実現のための手段などに悪質性があるとカスタマーハラスメントになる可能性があるんだよ。
カスタマーハラスメントの判断基準は、各事業所によって違いがあります。
事業所内で、あらかじめカスタマーハラスメントの判断基準を明確にし、事業所内での考え方、対応の仕方を共有しておきましょう。
・対応は一人では行わない。
・介護サービスの範囲を超える過剰な要求などに対して『社会通念上受け入れられないことは、きちんと断る』という毅然とした態度を示す。
・悪質性の高いものは、警察・弁護士などに相談する。
・契約を解除するなど。
契約解除を行う場合
介護保険サービスにおいては、正当な理由なくサービス提供を拒んではならないとされています。
・事業所の現員からは利用申込に応じられない場合。
・利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合。
・利用申込者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難な場合。

サービス継続に困難があっても、担当者会議等で対応策を検討するなど、サービス提供を継続するための努力をしなくてはいけないんだよ。
正当な理由により、解除しなければならない場合には、契約書の記載事項に即して対応することが大切です。
その際には、解除の理由、手続きについて利用者家族に説明し同意を得たうえで、契約書又は重要事項説明書に記載された一定の予告期間等の手続きを守る必要があります。
また、利用者へのサービス提供が止まらないように、ケアマネ等へ連絡し、他の事業者を紹介するなどしなくてはいけません。
カスタマーハラスメントについて詳しく解説しています。下記記事を参考にしてください。⇓⇓

サービスの質の向上の為にアンケートにご協力ください。
1分で終わります。アンケートはこちら
まとめ
クレームは、情報として貯めていく事で、リスク管理や業務改善として活用する事ができます。
解決したら終わりにするのではなく、記録をして、今後の業務に活かしていきましょう。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫


この研修内容はPDFとして簡単に印刷できるから社内研修の時に使ってね。
本資料は、介護の現場での共有・活用を目的として作成しています。 以下のようなご利用はご自由にどうぞ:
・印刷して使用
・職場内での回覧・配布
・個人での保存・参照
ご遠慮いただきたいご利用
以下の用途でのご使用はお控えください:
・無断転載(Webサイト・SNS等への投稿など)
・無断での再配布・再編集(PDF配布、内容の加工などを含む)
・商用利用(有料教材・商品の一部としての使用など)
文章・図表などの無断引用(出典・文脈の明示がないままの一部使用など)
外部でのご紹介・引用について
外部メディア・資料・SNS等で当資料の一部を引用・掲載される場合は、 必ず以下のように出典を明記してください:
※文脈を歪める形での引用や、誤解を招く編集はご遠慮ください。 不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください: info@care-power-lab.com
★リンク・ご紹介は大歓迎です!
皆さまのつながりが、介護現場の力になります。
アンケートの実施
記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。
ブログの質の向上に役立てさせていただきます。
アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩
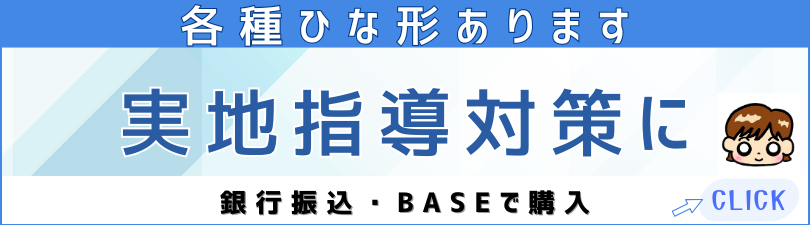
参考資料:厚生労働省【カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会】000915233.pdf (mhlw.go.jp)