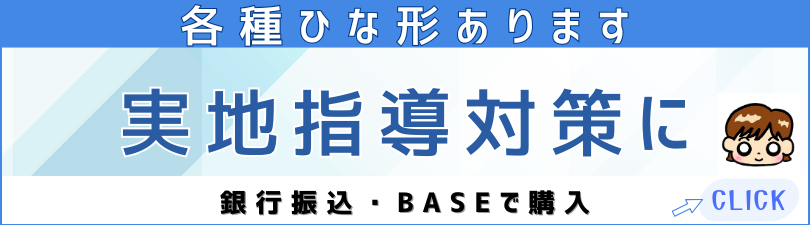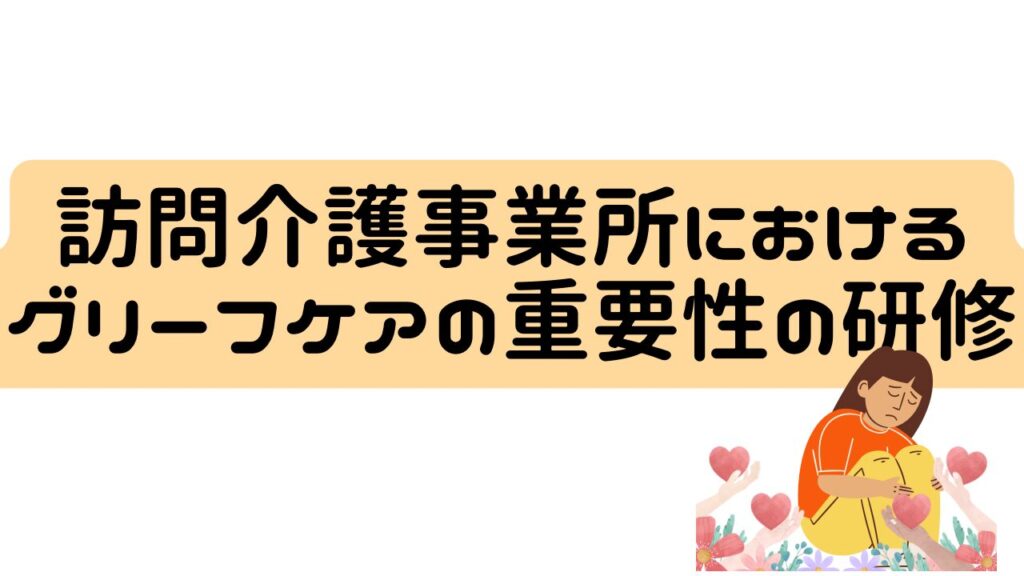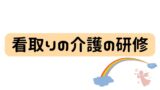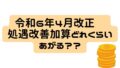※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷
✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる
✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

グリーフケアとは

今日はグリーフケアについて一緒に学んでいきましょう。

グリーフとは悲嘆(ひたん)という意味なんだよ。
グリーフケアは、死別などを経験したときに生じる悲しみや苦しんでいる人の気持ちに寄り添い、支えるためのケアです。
喪失(そうしつ)によって引き起こされる感情的な痛みを和らげ、自立する手助けを目指します。
グリーフケアは、喪失体験(死別、離別、病気など)を経験した人々が、その悲しみや苦しみ(グリーフ)を理解し、適切に対処するための支援を指します。
心理的なケアだけでなく、社会的なサポートも含みます。
グリーフケアの歴史
グリーフケアの始まりと発展: グリーフケアは、1960年代に欧米で生まれた考え方で、喪失感を経験した人々、特に死別を経験した人々の悲しみを理解し、彼らが再び立ち上がり、自立するのを助けることを目的としたケアになります。
日本での認知: 日本では、1970年代からグリーフケアに関する研究が始まりました。2005年のJR西日本福知山線脱線事故をきっかけに、グリーフケアの必要性が広く認識されるようになりました。その後、2009年には日本で初めてグリーフケアを専門とした教育研究機関「グリーフケア研究所」が設立されています。
グリーフケアの必要性

喪失は、誰でも人生で必ず起こる事であり、それを経験することは避けられないんだ。
その影響は個々の人によって大きく異なりますが、一部の人々はその結果として深刻な心理的苦痛を経験します。
喪失による悲しみは、睡眠障害や食欲低下、頭痛、抑うつ症状など、心身の健康に大きな影響を及ぼすことが知られています。
親しい人を亡くした悲しみは、心だけでなく、体や行動、認知面にいろいろな症状をもたらすと言われています。
【心の症状】
・悲しさ、寂しさ、憂鬱、不安
・怒り、敵意
・幻覚など
【体の症状】
・食欲不振
・睡眠障害
・疲労感
・頭痛や嘔吐、動悸
・アルコールや薬への依存など
【行動や認知面の症状】
・注意力低下
・号泣
・行動パターンの喪失など
このような症状は決して健康的な状態ではありません。
グリーフケアを行い再び日常生活に適応できるように援助する事が必要とされています。
訪問介護でのグリーフケアの具体的な活用方法
グリーフケアでは、普段から利用者家族と接する事の多い訪問介護のヘルパーは非常に重要な役割を果たします。
利用者を亡くし、強い悲しみや不安を感じている家族の心のケアも必要不可欠だからです。
ヘルパーは、グリーフケアを理解しておく必要があります。

私たちは具体的にはどんな事をすればいいの??
具体的には、以下のような方法でグリーフケアを活用することができます。
聞き役に徹して相手の気持ちを受け止める
- 聞き役に徹して、相手の気持ちを受け止める。
- 悲しみを我慢せず吐き出せるような場を作る。
- 相手の言葉に心を傾け、うなづきなど「あなたの話を聞いているよ」という意思表示をする。
- 「悲しいですね」といった相手の発した感情の言葉をくりかえす。

傾聴と共感・感情を吐き出しやすい雰囲気作りが大事なのね。
その人の気持ちを勝手に解釈しない
悲しんでいる人を目の前にすると早く元気になってもらいたいと考えてしまいます。また、無理に会話を続けようとしてしまい、
「辛いけど頑張って」
「早く元気になってね」
などの言葉をかけてしまいがちです。
しかし、元気になってもらいたいと思っているのは「自分の気持ち」であり、目の前の人の気持ちではありません。

悲しみを一緒に感じ、寄り添う事が大事なんだね。
グリーフケアで重要な事
グリーフケアの基本は、共感・寄り添いです。
遺族に共感して価値観を押し付けないことが重要です。
家族との別れだけではない
- 友人、ペットとの死別や離別。
- 離婚や子供との生き別れ。
- 失踪や行方不明など生死がはっきりしない状態での別れ。
- 失恋やケンカ別れなど。
長く生活を共にしてきた家族やパートナーとの別れは、残された人の生きる意味、さらには存在価値すらも見失うほどの深い悲しみをもたらします。
また、最近ではペットロスという言葉があるように、飼っているペットも家族の一員として扱われています。
しかし、周囲からはペットを「ただの動物」と軽く扱われやすい傾向があるため、つらい気持ちを理解されずに、深い悲しみの中で苦しんでいる人もいます。
グリーフケアはヘルパー自身に対しても必要
遺族だけではない
ヘルパーの悲嘆ケア: 死という経験は、想像以上に心と体に影響を及ぼすため、介護スタッフにも悲嘆ケアが必要です。
利用者の死によってヘルパー自身も、悲しみや喪失感を経験することが多くあります。
そのため、自分自身の感情を理解し、適切に対処するための自分自身へのグリーフケアが必要です。

私も喪失感で体調が戻らない事が多いわ…。

スタッフ同士で寄り添う事も大切だよね。
自分自身で行うことができるグリーフケアの手段を以下に示します。
- 自分の感情を認識し、涙を抑制しない。
- 同僚や上司との会話を通じて苦しみを分かち合う。
- 自分の感情を紙に書き文章にまとめる。
- 精神科医や専門家のカウンセリングを利用する。
- 健康的な食事と規則正しい生活を心掛ける。
- 運動を通じて汗を流し、ストレスを発散する。
自分の苦しみを受け入れ、それを内に閉じ込めずに外に出すことが重要と言われています。
また、心と体は密接に関連していますので、食事の内容に注意し、十分な睡眠をとり、適度な運動を行うことは、自分自身を守る基本的な心構えと言えます。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

まとめ
訪問介護事業所でのグリーフケアは、喪失体験をした利用者家族への必要な支援を行うことです。
その背景や意義、必要性を理解することで、より効果的なケアが可能となります。
また、グリーフケアは、喪失体験をした全ての人々、つまり利用者家族だけでなく、訪問介護事業所のヘルパー自身にも必要なケアです。
これは、私たちが悲しみを理解し、適切に対応するための重要な手段となります。

この研修内容はPDFとして簡単に印刷できるから社内研修の時に使ってね。
※この資料は「訪問介護の現場で共有・活用」していただくために作成しています。
印刷・保存・職場内での回覧はご自由にどうぞ。
※以下の行為はご遠慮ください:
・無断転載(サイトやSNSへの転写など)
・無断での再配布・再編集(PDF配布や加工含む)
・商用利用(有料教材や商品への転用など)
ただし、外部に掲載・共有される場合は「出典: https://care-power-lab.com 」と出所を明記してください。 不明な時は遠慮なくご連絡ください。→ info@care-power-lab.online
★当サイトへのリンク・ご紹介は歓迎しております。
【参照サイト】上智大学グリ-フケア研究所:https://sophia-griefcare.jp/about/
【参照サイト】日本グリーフケア協会:https://www.grief-care.org/about.html
アンケートの実施
記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。
ブログの質の向上に役立てさせていただきます。
アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩
【PR】