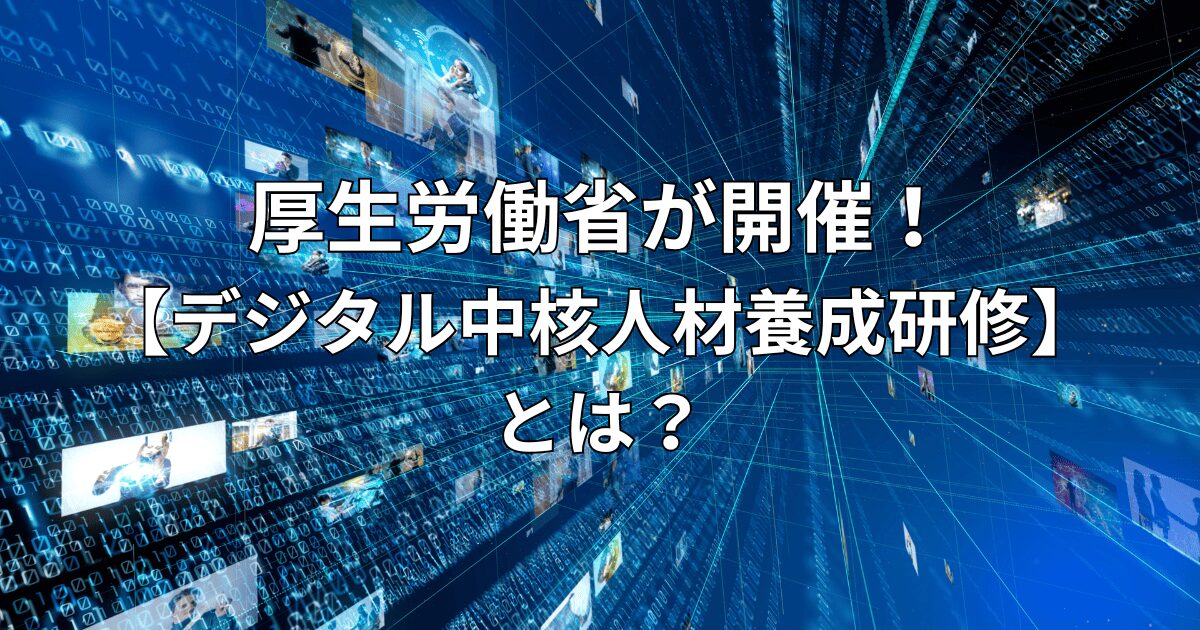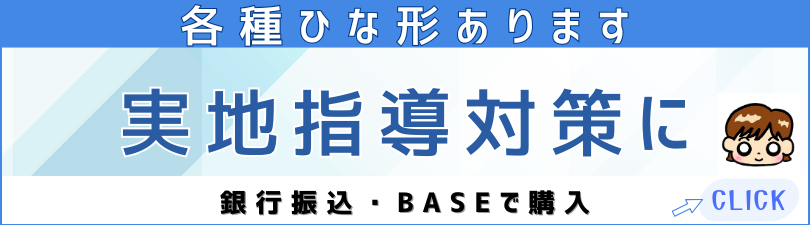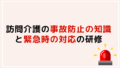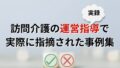※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
デジタル中核人材養成研修とは
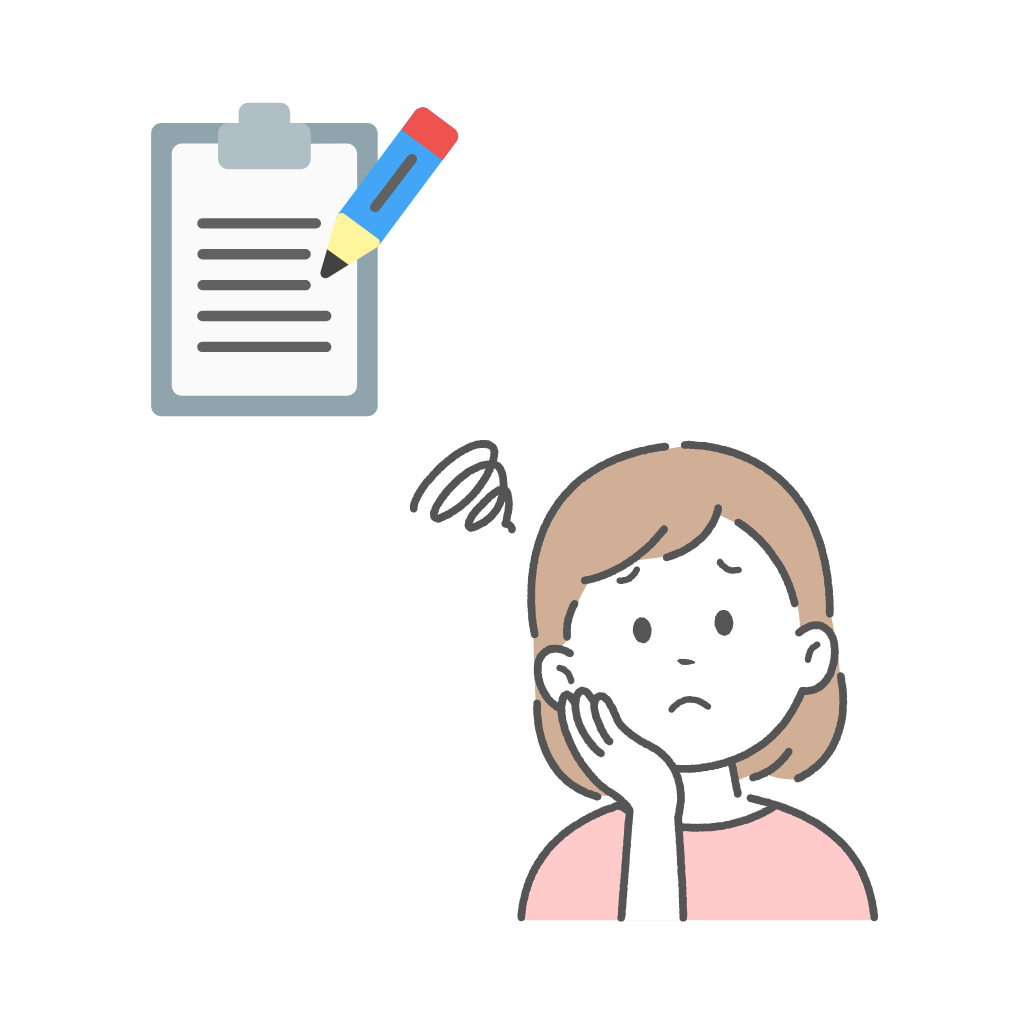
「もっと記録が簡単になったらいいのに」
「事務的な処理に時間がかかりすぎて困っている」
そんな声が全国からあがっています。
厚生労働省は、そうした現場の声を受けて、令和7年9月から「デジタル中核人材養成研修」という研修をスタートさせるようです。
➤ https://www.mhlw.go.jp/content/001553074.pdf
この研修の目的は?
介護職員の人数が年々減る一方で、仕事の量や責任は重くなっているのご存じの通り。
そこのままでは「人手不足」と「働く人の負担」がますます大きくなってしまいます。
そこで、介護の仕事を効率よく、さらに利用者に寄り添えるようにするために、デジタル技術の活用が重要だと考えられています。
🔻 例えば…
- タブレットで記録をとってクラウドに保存すれば管理も楽。
- ネットで職員同士が情報を共有できれば、申し送りがスムーズになる。
こうした工夫を現場に広める“旗振り役”を育てるのが、この研修の狙いです。
「デジタル中核人材」って?
聞き慣れない言葉かもしれません。

簡単に言うと、「現場の困りごとを見つけて、デジタル技術を上手に使い、働きやすい環境をつくる人」の事だよ。
🔻 例えば…
- 「記録時間を減らして、もっと利用者と会話がしたい」
- 「この作業は1人だと大変。デジタル技術で手助けできないかな?」
そういう声を拾い上げて、道具やシステムを導入する橋渡しをする人です。
リーダーシップを持ってチームをまとめる役割も大切になります。
「デジタル中核人材養成研修」は、厚生労働省が中心となって行われる、介護の現場で新しい技術や考え方を取り入れ、業務をより良くしていくためのリーダーを育てる研修です。
研修の内容
研修では大きく3つのことを学びます。
1.介護のデジタル技術を使いこなす意味を深く理解する: 介護の現場で、なぜ新しい技術を取り入れる必要があるのか。また、介護テクノロジーを効果的に使うことで、より質の高いケアを目指すことの大切さを理解します。
2.仕事をスムーズにするための考え方を学ぶ: 「今の仕事をもっと効率よく、安全にできないか?」と、現場の課題を見つける方法を学びます。また、チームみんなで協力して業務改善に取り組むための、リーダーシップの基本的な知識やスキルも身につけます。
3.利用者一人ひとりに合ったケアを考える力を高める: デジタル技術を使うことで、利用者が「自分でできること」を増やしたり、もっと快適に、そして安全に過ごせるようにしたりする方法を学びます。具体的には「アセスメント力」を高め、科学的な視点から個別性の高いケアを実現するための知識を学びます。
訪問介護の現場での具体的な活用例
🔻 例えば…
訪問サービスでは1件ごとに記録を残す必要があり、その作業時間も膨大です。
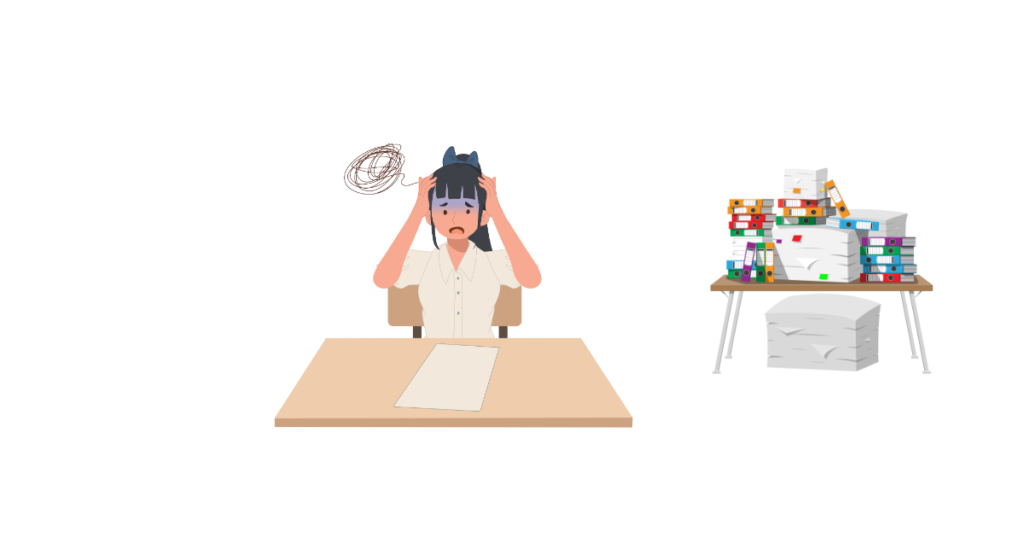
タブレットや音声入力を活用すれば記録時間を短縮できます。
また、サービス提供責任者はシフト調整や緊急時の連絡に多くの時間を割かれていますが、チャットツールやクラウド型シフト管理システムを導入することで、効率化が図れます。
受講の流れ
🔻 研修への申し込みから修了までの主な流れは次の通りです。
- 受講の申し込み: 「参加条件」を満たしているか確認し、希望の研修セット(日程)を選んで申し込みます。
- 事前課題の学習: オンライン授業が始まる前に、ウェブ動画やオンデマンド動画を計画的に視聴し、必要な知識を学びます。
- オンライン授業の受講と職場での実践: 3日間のオンライン授業に出席し、その合間にご自身の職場で課題に取り組み
- 確認テストの受験: 研修で学んだ内容がどれくらい身についたかを確認するためのテストを受けます。
- 修了: 事前課題の完了、オンライン授業への出席、課題の提出、確認テストの合格という全ての条件を満たすと、研修は修了となります。
参加した人の声

現場の職員も経営層も一緒に改善を考えるようになって、チャットツールを活用し業務が効率化しました。

デジタル技術はハードルが高いと思っていたけど、意外と簡単で便利でした。成功体験から新しいツールの導入につながりました。
などといった声があがっているようです。
参加条件と費用
✅ 参加条件
この研修に参加できるのは、以下の2つの条件をどちらも満たしている方です。
1.介護サービス施設や事業所で、3年以上働いた経験がある方。
※ここでいう「勤務経験」は、介護の仕事だけでなく、施設の事務職や法人の本部での勤務なども含みます。
2.今、お勤めの職場で「もっと仕事を良くしたい」と考えていたり、これから介護のデジタル技術(介護テクノロジー)を取り組みたい、または既に関わっている方。
✅ 費用
➤ この研修は、参加費用がかかりません。無料です。
全国から合計1,500名の方が参加できます。定員になり次第、申し込みは締め切られるようです。
申込み方法
「ケアウェル」という、インターネット上の研修管理システムを使って申し込みます。
このシステムは、日本介護福祉士会の会員ではない方でも無料で使うことができます。
「ケアウェル」に登録する際は、ご自身のメールアドレスを使用します。
職場で使うメールアドレスや、携帯電話会社のアドレス(例:@docomo.ne.jp @ezweb.ne.jpなど)は使えないので注意が必要です。
すでにケアウェルを使ったことがある方は、その時のIDとパスワードでログインして申し込みます。初めての方は、「ケアウェル(非会員)個人アカウント」の作成から始められます(これも無料です)。
詳しい申し込み方法は、日本介護福祉士会のホームページでも案内されていますので、ご確認ください。 ➤https://www.jaccw.or.jp/news/20250815
興味があけど参加できるか不安…。
困ったときの相談先
この研修はオンラインで行われるため、普段パソコンやZoomを使い慣れていない方にとっては「ちゃんと参加できるかな…」と不安に思うこともあるかもしれません。
また、研修が終わった後に「じゃあ実際に職場でどう進めればいいの?」と悩む場面も出てきます。
※ 厚生労働省はサポートのための相談先や参考サイトを案内しています。
研修を受ける前に困ったら
「効率化って具体的に何をするの?」
→ 厚労省の「介護分野における生産性向上ポータルサイト」を見ると、事例や導入のヒントが分かります。 https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/index.html
「Zoomを使ったことがなくて不安…」
→ YouTubeで「Zoom 使い方」と検索すれば、基本操作を説明した動画がたくさんあります。初めての方でも安心して予習できます。
研修が終わった後に困ったら
「自分の職場でも改善を始めたいけど、具体的にどうすれば…?」
→ 各都道府県にある「介護生産性向上総合相談センター」で相談できます。業務改善の具体策やICT導入のアドバイスを専門スタッフがサポートしてくれます。➤https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/pf/soudan/info.html
このように、研修は「学んで終わり」ではなく、受講前の不安解消から受講後の実践サポートまで、段階に応じた相談先が用意されています。
最後に
この研修で学んだことは単なる「一時的なスキル」ではなく、今後のキャリア形成にも直結します。
介護業界では「デジタルに強い人材」はますます求められています。
また、介護現場の業務改善をリードできる職員は、実地指導や加算要件への対応でも高く評価される可能性があります。
単なる効率化にとどまらず、事業所全体の成長につながる力を身につけられるのが、この研修の大きな価値となりそうです。
研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン