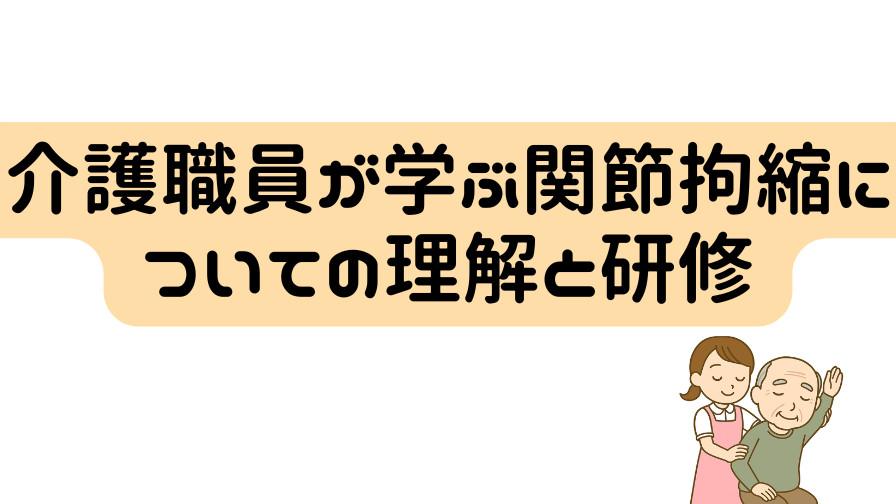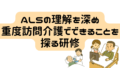※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
この記事は情報提供のみを目的としており、医療上の診断や治療の代替を意図するものではありません。
この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷
✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる
✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫


はじめに

関節の拘縮を起こしている利用者は非常に多く、介護スタッフとして着替えや移乗の介助を行う際には利用者にケガをさせないように、特に注意が必要です。
本日は、安全に介助を行えるように関節拘縮を一緒に学んで行きましょう。
拘縮とは


「関節拘縮(こうしゅく)」を起こしている利用者さんが多いんだけど、介護職としてどんなことに気を付ければいいのかな?

今回は「関節拘縮」とは何か、拘縮があることでどんなことに困るのか、拘縮に対して介護職ができることを考えてみよう!
拘縮とは、関節の周りにある筋肉や靭帯・皮膚などが原因で起こる関節の可動域制限のことです。
すなわち
本来動かせるはずの関節の可動範囲よりも動かせる範囲が狭まっている状態です。
拘縮の種類
大きく「生まれつき(先天性)の拘縮」と「後天性の拘縮」に分けられます。
後天性の拘縮は病変部位から
①皮膚性拘縮
②筋性拘縮
③靭帯性拘縮
④腱性拘縮
⑤関節性拘縮
の5つに分けることができます。
身近な拘縮
- 重度な火傷が回復する際に皮膚が引きつるために起こる関節可動域制限(皮膚性拘縮)
- 骨折の治療のため長期間、関節を固定していると、関節・靭帯・筋肉が硬くなるために生じる関節可動域制限(筋性拘縮)
- 四十肩、五十肩

拘縮って意外と身近によく起こるものなのね~

そうなんだ。要介護の人や寝たきりの人だけに生じるものではなく、家族や友人、自分自身も経験があるような身近なものだね。
拘縮へのアプローチ
拘縮へのアプローチは病変部位や原因によって異なります。
運動療法や物理療法(温熱・超音波療法)、マッサージ、鍼灸治療などがあります。
拘縮の改善にかかる期間

拘縮の程度や要因により改善にかかる期間は変わります。
軽度:数週間から数カ月で改善
中等度:数カ月から半年以上
重度:数年単位でのリハビリテーションが必要であり完全な回復が難しいことがある
※重度拘縮の主な原因としては、長期間の不動(寝たきりやギプス固定など)、神経障害(脳卒中や脊髄損傷など)、外傷などが挙げられます
拘縮の進行を左右する要因
1.年齢
2.罹病期間(りびょうきかん)
3.日常生活活動能力
4.麻痺・痙縮(けいしゅく)
5.痛み
6.浮腫
要因は大きく6つあります。それぞれ詳しく見てみよう。
年齢
健康な人でも加齢に伴い、腕が上がりにくくなるなど関節の可動域が低下します。
これは、関節周囲の主要な構成成分であるコラーゲン繊維が加齢によって変化することが主な原因と考えられています。
また、加齢に伴う筋力低下などにより運動量が減少、関節を動かさない状態が長期化することも二次的な要因として関与しています。
罹病期間
病気や怪我により安静にしなければならない期間が長期化することで可動域制限が生じやすくなります。
日常生活活動能力
日常生活能力が低いと関節運動の時間が少なくなり、関節可動域制限を起こしやすくなります。
麻痺・痙縮
脳血管疾患において、麻痺の回復段階で見られる筋収縮が持続して起こり、関節を動かさないでいる事が、関節可動域制限の発生や進行に関与していると考えられています。
痛み
痛みにより筋肉に力が入った状態が持続することで関節の不動も継続されます。また力が入った状態が続くことで痛みが生じ、痛みの悪循環となり、関節可動域制限も進行しやすくなります。
浮腫
浮腫みの発生は筋肉を変化させるため、関節可動域制限の発生に直接的に影響を及ぼす可能性があります。
また、痛みを伴う場合は関節を動かさなくなり、浮腫みも助長することとなり、悪循環となります。
介護を必要としている高齢者は複数の影響を受けやすい状況になっている事を理解しておきましょう。
拘縮の生活への影響
関節拘縮が起こると生活にどんな影響があるのか、具体的にどんな場面で困るのか見てみましょう。
入浴・清拭

重度の関節拘縮がある場合、拘縮している部位は汗や汚れがたまりやすく、皮膚障害を引き起こす可能性があります。
特に、手指を握り込んでいる場合、本人の爪が皮膚を傷つけることがあります。
無理に手指を広げようとすると痛みが生じ、その結果さらに強く握り込んでしまい、ケアが難しくなることも。
そのため、拘縮部位の清潔を保つことが重要です。入浴や清拭の際は、たっぷりの泡を使い、優しく洗うよう心がけましょう。
皮膚を強くこすらないことが大切で、皮膚が弱っている場合は、こすると傷つきやすくなりますので特に注意が必要です。
おむつ交換
股関節拘縮を起こしている方のおむつ交換では、無理に足を開こうとすると骨折や脱臼のリスクがあります。
痛みを感じさせない範囲で、ゆっくりと動かしましょう。
仰向けでの作業が難しい場合、側臥位にしておむつ交換を行うと負担が軽減されます。この姿勢では足を無理に開く必要がなく、利用者もリラックスしやすいです。
「少し足を動かしますね」
「痛くないですか?」
など、利用者に安心感を与える声かけを行い、不安を軽減します。
拘縮があると皮膚が圧迫されやすいため、おむつ交換時には皮膚の状態を確認し、洗浄をし清潔を保つようにします。
洗浄後はしっかりと乾燥させ、保湿剤を使用することも効果的です。
更衣

肩・肘・膝・股関節が拘縮してしまうことで着替えが難しくなります。
また、衣類に腕や足を通しにくくなります。
拘縮が片側の場合は拘縮のある側から腕を通すようにしましょう。
脱がすときは、逆の手順を行います。
健側→患側の順で袖を抜くと楽に介助できます。
両腕が拘縮している場合は、拘縮の弱い側から先に脱ぎ、拘縮の強い側から先に着せましょう。
拘縮が両側である場合や重度な場合には、ゆったりとした服や前開きの服装にするなどの工夫が必要になってきます。

移乗
股関節や膝関節、足関節の拘縮があると立っていることが難しいだけでなく、座った姿勢を保つことも困難となります。
ベッド端での座位保持は不安定となり、移乗の介助がより難しくなります。
また、肘や手首・指の関節拘縮により、手すりを保持できなくなります。
端座位の保持が難しい方の移乗をする場合は無理をせずに2人介助で行うなど、安全を確保して行いましょう。

※端座位…椅子やベッドなどの端に、足をおろして座った状態。足が床についている為安定感があり、食事をする際に適しています。
※二人介助を行う際には必ずサービス提供責任者に相談を行い、ケアマネに二人介助の必要性があると伝えてもらいましょう。ケアマネも必要性があれば、すぐにプランの変更をしてくれます。
高齢者は骨粗鬆症で骨が脆く(もろく)なっていることがあるので、移乗時にかたくなっている関節を無理に動かそうとすることで骨折してしまう危険性があります。移乗するときは利用者の表情を見て痛みがないか、よく確認しながら介助をしましょう。
脊髄損傷者への拘縮の影響
脊髄損傷の方は関節拘縮により、日常生活の自立度が大きく左右されます。
例えば、体幹が不安定な場合でも肘を正常かそれ以上に伸ばすことができれば、座位姿勢が不安定でも腕で支えることができます。
しかし、ほんの少しでも拘縮があると座位を保持することが難しくなります。
膝を伸ばした状態で股関節をしっかりと曲げることができれば、長座位での移乗や下衣の着脱を楽に行えるようになります。

※長座位…足を伸ばして座っている状態
脊髄損傷の方は麻痺で動かすことができない関節も関節拘縮を予防し、関節の可動域を維持・拡大することが日常生活の自立度に大きく影響します。
拘縮予防

拘縮は予防することがとても重要なんだ。
介護職として拘縮予防に対してどんな支援ができるか考えてみよう。
クッションの活用

例)手指拘縮予防クッション:手指の拘縮を防ぐために使用される補助具です。
- 手指の間を広げる
指が握り込んでしまうのを防ぎ、指の間に適切なスペースを保つことで、拘縮の進行を抑えます。 - 快適な素材
柔らかい素材で作られており、長時間使用しても手に負担がかからないように設計されています。 - 衛生的なケア
汗や汚れが溜まりにくい通気性の良い素材が使われているものもあり、清潔を保つのに役立ちます。 - リハビリの補助
手指のリハビリやストレッチをサポートするために使用されることもあります。
他に拘縮予防や褥瘡予防の目的で様々なクッションを用いて姿勢を整えます。
長時間同じ姿勢で過ごすのは苦痛を伴うため、いくつかの姿勢を計画的に交換していきます。医師・リハビリ職からの指示を確認しておきましょう。
正しいポジショニング
正しい姿勢・ポジショニングは身体の圧が分散し、筋肉の緊張が弱まります。

≪肩のサポート≫
肩の後ろに隙間があると、不安定になり、拘縮が進行する可能性があります。手を入れて肩の後ろの隙間を確認し、もし隙間がある場合はタオルやクッションで埋めて、筋肉の緊張を和らげましょう。肩が楽になると肩甲骨が開き、上半身の反りや硬さが緩和されます。
≪腰のサポート≫
腰から背中下に隙間があると、骨盤が前傾して呼吸がしづらくなります。呼吸がしづらくなると全身が緊張し、拘縮が進行します。肩と同じように、腰の下にも手を入れて隙間を確認しましょう。隙間があれば、膝と股関節を立てることで、腰がしっかりとマットレスに接し、安定した姿勢を保てます。
どのような姿勢で休むのが良いのか、リハビリ職や看護師などから指示がある場合は必ず確認しておきましょう。
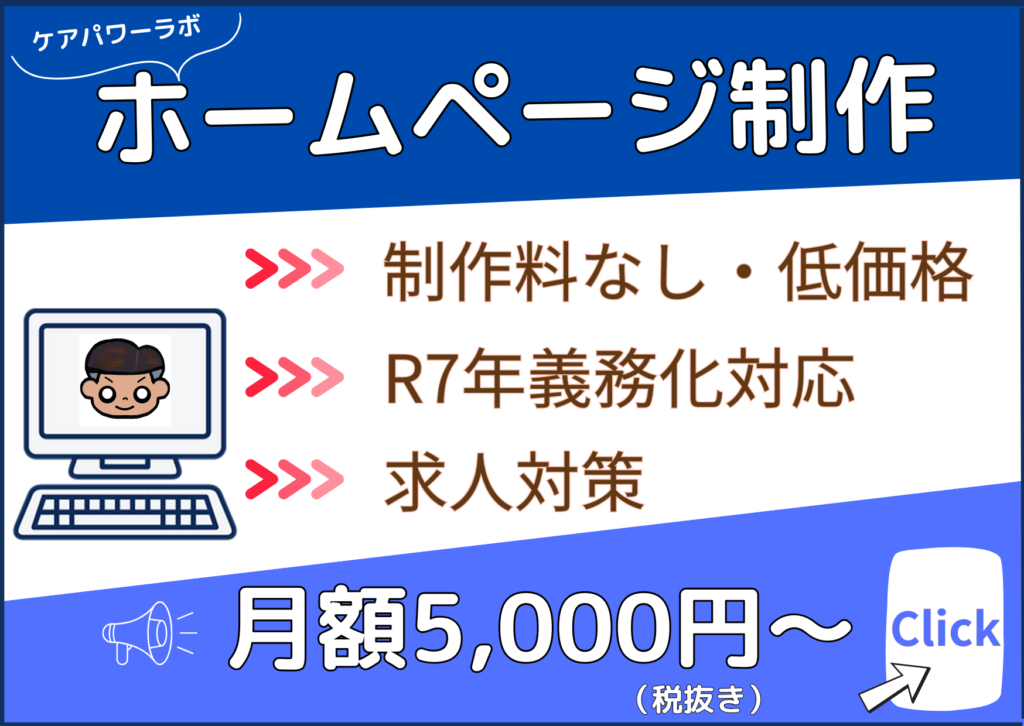
関節可動域運動

拘縮を予防するためには可能な限り全ての関節に対して行います。
1つの関節に対して全可動域を5回、最低1日1回実施します。
動かす際は利用者の表情を見ながら、ゆっくりと丁寧に実施します。利用者が自身で動かせる部分は自身で動かしてもらうようにしましょう。
ご家族・ご本人には拘縮予防や関節可動域訓練など必要なケア方法についてリハビリ職や看護職などから入院中などに説明をされている場合があります。
訪問介護職員が運動を行うことはないかもしれないですが、注意点は押さえておきましょう。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

まとめ
関節拘縮について学ぶことは、安全で効果的な介助を実現するための第一歩です。
介護スタッフとして、利用者一人ひとりの状態を理解し、適切なサポートを提供することは、心と技術の両方が問われる重要な役割です。
今日学んだ知識を活かし、より安心して介助を行える環境を作り上げていきましょう。
小さな気配りが、大きな安心につながります。
一緒に、利用者が快適に過ごせる毎日を支えていきましょう。
研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン
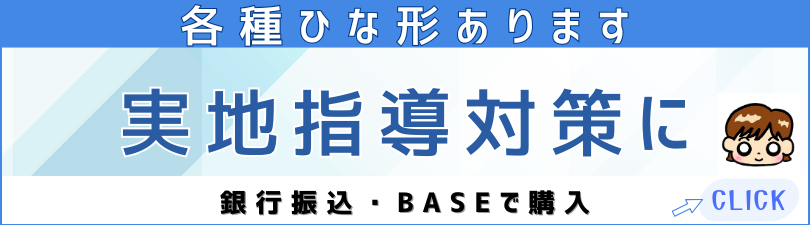
アンケートの実施
記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。
ブログの質の向上に役立てさせていただきます。
アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩
【参考文献】
・関節可動域制限 病態の理解と治療の考え方/編 沖田実/株式会社 三輪書店
・脊髄損傷マニュアル リハビリテーションマネージメント 第2版/神奈川リハビリテーション病院 脊髄損傷マニュアル編集委員会/医学書院
・田中義行(2016) オールカラー介護に役立つ!写真でわかる拘縮ケア