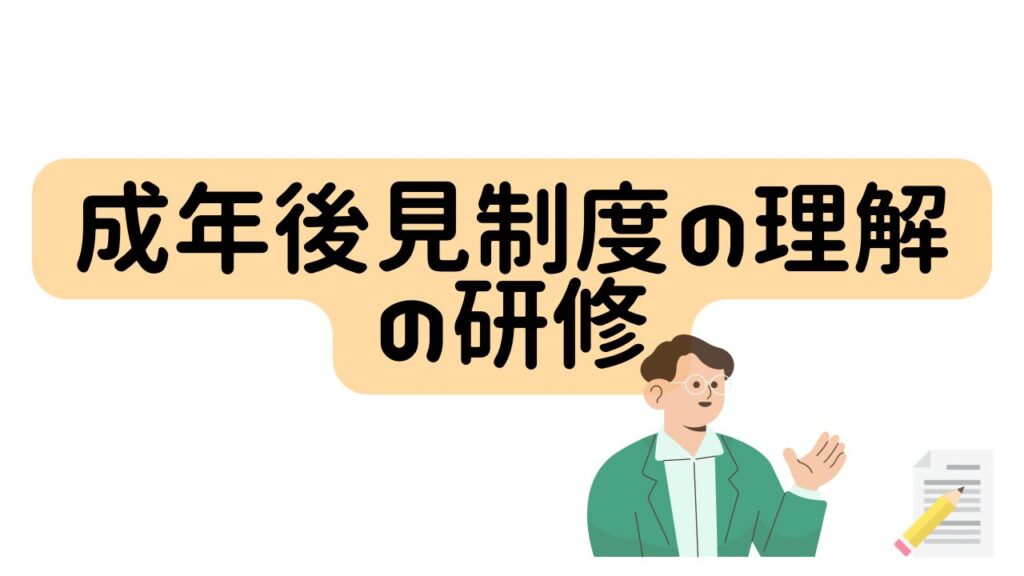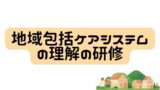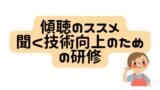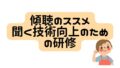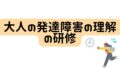※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷
✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる
✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

参考資料:厚生労働省【ご本人・家族・地域のみなさまへ(成年後見制度とは)】https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/

成年後見制度ってよく聞くけど
むずかしいんだよね…。

高齢社会の日本ではこれからますます重要な制度になっていくんだ。いっしょに頑張って学んでいこう
成年後見制度(せいねんこうけん)って?
認知症・知的障がいがある方は、お金の管理や法律行為などをすることが難しいことがあります。
このような方の意思を尊重した支援を行い法的に保護しようとする制度が【成年後見制度】です。
2つの制度がある
任意後見制度(にんいこうけんせいど)
認知症などの場合にそなえて判断能力があるうちに、みずからが選んだ人にしてもらいたいことを決めておく制度です。
法定後見制度
判断能力が不十分になってしまった後に周囲の人が申請をおこなって、裁判所が保護してくれる人を選ぶ制度です。

2つの制度の特徴を理解しておこう
【任意後見】
・判断能力があるうちに決める
・本人が自分の意志で決める
【法定後見】
・判断能力が不十分になった後に決める
・裁判所が決める
![]()
法定後見制度3つの種類
法定後見制度では障がいや認知症状の程度によって3つの種類があります。
後見(こうけん)
判断能力がまったくなく、自分の財産を管理・処分することができない。
補佐(ほさ)
判断能力がまったくないわけではないが、いちじるしく不十分、自分の財産を管理・処分するには常に助けが必要。
補助(ほじょ)
判断能力が不十分、自分の財産を管理・処分するには常に助けが必要。
※種類によって後見人が手伝う範囲がかわります。具体的な細かい内容は家庭裁判所がきめます。
成年後見人とは?
十分な判断ができなくなった本人に代わって契約をしたり・財産の管理などをします。
・保護をする人 ➡成年後見人
・保護を受ける人➡被成年後見人(ひせいねんこうけんにん)

法定後見制度ではどんな人が選ばれるのかしら??
親族
成年後見人に選ばれるのは本人の親族であるケースが多いです。
裁判所も【後見人は身近な親族を選任することが望ましい】という考えをだしています。
法律・福祉の専門家
親族がいない場合や法律面での問題がある場合では、弁護士などの専門職が選ばれることがあります。
【弁護士】【司法書士】【社会福祉士】が多く選ばれています。
専門家であるため安心して任せられるメリットがあります。
市民後見人
地域の自治体などが実施する研修を受け知識や姿勢などを習得した一般市民のことをいいます。
身近な立場で生活を支援する市民後見人にかかる期待は大きくなっています。
法人
社会法人や弁護士法人などの法人が成年後見人等になることも可能です。
法人が成年後見人になると複数人で業務をおこないます。

未成年者・破産者などは成年後見人にはなれないんだよ
成年後見人が行うこと
成年(法定)後見人が行うことは大きく3つあります。
財産管理
貯金・株券の管理や本人が所有している不動産の管理などをおこないます。
・家賃の支払い
・納税
・介護サービス費用の支払い
・病院の診療代の支払いなど
身上監護(しんじょうかんご)
本人の安全と健康を守る必要があるため、本人に代わって契約行為などをおこないます。
・介護保険サービスの契約
・病院の入退院の手続き
・すまいの確保の手続きなど
事務報告
成年後見人は行った事務について家庭裁判所に報告をします。
後見人が行ったことはしっかりと管理されます。
後見人等の職務ではない事(できない事)

後見人に選ばれたとしてもすべてが本人に代わってできるわけではないんだ
※後見人にはできないことが色々あるのですが、ここでは代表的なものを取り上げていきます。
事実行為
本人のために直接働きかける行為のことをいいます。
後見人は事実行為をする義務はありません。
・入浴の介助
・掃除・洗濯
・病院までの送迎
・食事をつくるなど

後見人は訪問介護事業所と契約をするなど、必要なサービスをうけられるように手配するのね
医療行為に関する決定・同意
入院の手続きなど契約を行う事はできますが、入院の決定を後見人が行う事はできません。
また医療行為の同意をすることもできません。
・入院をさせる
・手術の同意をするなど
身分行為
本人の婚姻・離婚などは本人がきめる事であるため、代理も取り消しもできません。
・婚姻、離婚
・養子縁組
・遺言など

勝手に結婚させられたら嫌だわ…
法定後見制度をつかうには
成年(法定)後見制度利用までのおおまかな流れを解説します。
申し立て
本人の住所がある家庭裁判所へ必要書類を提出します。
書式は家庭裁判所のホームページからダウンロードもできます。
また、医師の診断書も必要となります。

診断書だけでは判断がむすかしい場合は【鑑定書】というより詳しく書かれたものを求められる事があるんだ
審判
裁判所の職員が本人や家族から事情や状況を聞き取ります。
その内容などから裁判官が総合的に判断し結果をくだします。
後見人が必要となった場合はもっとも適任と思われる人が法定後見人に選ばれます。
制度の開始
開始が認められたら後見人は法務局に登録され開始となります。
相談窓口
訪問介護の仕事では今後、利用者本人や家族から『成年後見制度について聞きたいんだけど、どこに相談したらいいかわからない』といった相談をうける事があるかもしれません。
そのような場合は下記の相談窓口をご利用ください。
・地域包括支援センター
・市町村の相談窓口
・社会福祉協議会
・社会福祉士・司法書士・弁護士団体など

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

まとめ
訪問系の仕事では利用者から「あなたなら安心だから通帳をあずかってほしい」などと言われる事も多くあります。
しかし通帳を預かってしまうと思わぬトラブルに発展してしまう可能性があるため注意しましょう。
そのような場合は相談窓口へつないでいくといった事が重要となります。
また、後見人は家族と同様に利用者にとって安心できる心強い存在であり、介護スタッフと同じチームの一員でもあります。