※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷
✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる
✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。
≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

はじめに
介護を受ける利用者は病気やケガ等が要因となり、生活でのサポートを必要としています。
こうした利用者を単に
「お世話をしてもらう人」
と捉えがちですが、介護を受ける方もひとりの人間であり
「その人らしい生活」
を送る権利があります。
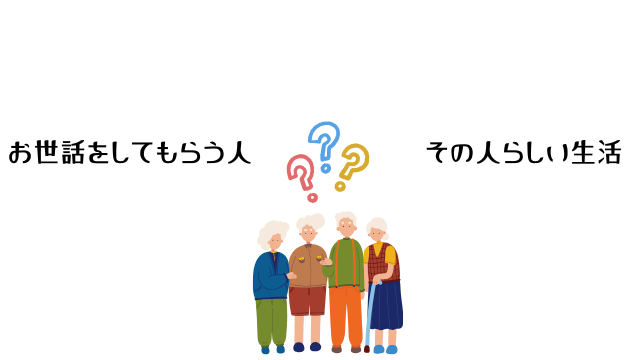

今回は尊厳を守るケアと、自立支援について高齢者の心理を踏まえながら具体的な方法を解説していきます。
尊厳(そんげん)とは
尊厳とは
その人の意思や価値観を大切にし、その人の事を認めること
を意味します。

例えば他のスタッフが自分の夢や目標を語ったときに、それをバカにしたりせず「それすごい!頑張ってね」と応援すること。
それがその人の尊厳を守る行動になります。
要するに
他の人の気持ちや価値をちゃんと認め、大切にすることが尊厳を大事にするという事になります。

相手を尊重する気持ちは、お互いの信頼や思いやりを深める関係の基盤になるんだ。

特に医療や介護分野では患者・利用者の尊厳を守ることが重要視されているよね。
介護保険制度の基本理念
この法律は加齢に伴って生ずる心身の変化によって起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
引用:介護保険法第一条

む、難しい…
平たくいうと
介護保険制度(介護保険法第一条)では、高齢者が尊厳を持ちながら、自分の力を活かして生活を続けられるようにする仕組みです。

第一条に挙げているくらいだから、とっても重要で大切な理念なんだ。介護に従事する人は覚えておかなければならない理念だよ。
介護保険の基本理念では、ただ単調に利用者のお世話をするのではなく
・本人のできることを尊重し
・本人の自立を支援すること
を特に大切にしています。

日本の社会全体でも高齢者の尊厳を守ることは大切なテーマになっているのね。
尊厳が守られないケア
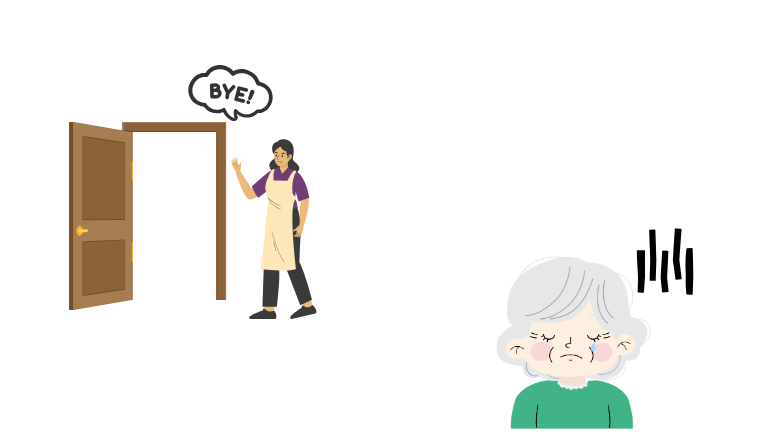
介護の現場では、忙しい中で利用者を単なる「介護の対象」としてみてしまうこともあるかもしれません。
しかし、介護を受けている利用者もひとりの尊厳ある人間であり、これまでの人生を生き、またこれからの人生を探している人なんです。
尊厳が守られないケアの具体例
訪問介護で尊厳が守られないケアとは、利用者の意思や価値観、個性、プライバシーなどが十分に尊重されていないケアを指します。
≪希望を無視するケア≫
利用者の希望を無視して一方的に進めるようなケアです。
例えば、本人が食事のタイミングを決めたがっているのに、介護者がスケジュール優先で強引に進める場合などが該当します。
≪選択肢を与えないケア≫
利用者に選ぶ権利を与えず、全てを介護者が決める場合です。
例えば、どんな服を着るか、食事の内容やお風呂に入る時間を勝手に決めてしまうことです。
≪プライバシーの侵害≫
利用者のプライバシーを配慮せず、例えば着替えや入浴を必要以上に人前で行う、またはその人の個人的な情報を他人に話すといった行為です。
≪一方的で効率重視のケア≫
介護者が時間や効率を優先し、利用者とのコミュニケーションをほとんど取らずにケアを進める場合です。
利用者がただ「される側」として扱われてしまう状況がこれに当たります。
≪利用者を子ども扱いする対応≫
利用者を対等な大人として尊重せず、命令口調や高圧的な態度で接することも尊厳を損ないます。

忙しいとつい利用者さんのことを考えるより、早く作業を終わらせようとしちゃう…。
尊厳を守るケアの具体例

尊厳を守るケアでは「本人の気持ちを尊重し、できる限り本人の意思を尊重する」ことを重視して行います。
具体的な場面でみてみましょう。
×:「寒いからこれ着ましょう!」と決めつける
⇒本人の好みや意思を無視すると存在価値を否定されたような気持ちになる
〇:「今日は寒いけど、どの洋服がいいですか?」と選択肢をあたえる
⇒本人の意思を尊重し、決定権をもたせることで存在価値を感じられるようにする
声掛けの方法を工夫したり、本人の意思を確認しつつ支援することがポイントです。

ついこちらが決めてやってしまいがちだけど・・・。

本人が「どのようにしたいか」意思を確認しながら声掛けすることが大切だね
尊厳を守るケアは、利用者の声に耳を傾け、その人らしさを尊重しながら、相手の希望や個性に寄り添う姿勢が大切です。
良いケアとは、利用者が「自分らしくいられる」と感じられるものです。
✅ 「このケア、大丈夫だったのかな…?」
そんなふうに不安を感じたことがある方は、
➤ 「これって虐待?」現場でよくあるグレーケアとその対処法はこちら
自立支援とは
自立支援の定義

介護の現場では「自立支援」という言葉が良く使われます。
具体的にはどのような意味なのでしょうか?
要介護状態になった者が「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」必要なサービスを提供することとされ、単に身の回りのお世話をすることを超えて、「高齢者の自立支援」を理念としている。
引用:平成12年版厚生白書概念(高齢者の自立を支える新しい介護制度)
厚生白書では
要介護者が可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援する
ことを理念としています。
平たくいうと
介護が必要な人ができることを増やし自分の力で生活できるように支援すること
と言えます。
・単に「お世話」するのではなく、「できることは自分でできるようにする」支援
・介護者が何でもやってしまうと、本来できる能力まで奪ってしまう可能性がある
自立支援の重要性
自立支援は、本人が可能な限り自分の力で生活できるようサポートすることを目的としています。
自立支援には4つのメリットがあります。
①自己肯定感の向上
自分でできることが増えると「まだできる」「役に立てる」と感じられ、自信につながる。
②QOL(生活の質)の向上
日常生活に積極的に参加できるようになり、趣味や社会活動の継続にもつながる。
③精神的な安定
他者に依存しすぎる不安が減り、自分の意思で選択できることで前向きな気持ちになれる。
④身体機能の維持・向上
動ける範囲を増やすことで、筋力やバランス能力の低下をふせぐ。

できることが増えると気持ちも前向きになるし、もっとやってみようって思えるのね

そうだね。そうすると生活が活発化されて生きがいにもつながりそうだね!
具体的なケア方法
自立支援の実践例
自立支援では「できることを増やし、できる範囲で自分の力を使う」ことを目標にします。
こちらもいくつか具体的場面をもちいてみてみましょう。
×:最初から最後まで本人の力以上に支えて歩く
⇒本人の力を使う機会が減り、筋力低下につながる
〇:「手すりに掴まりながら一緒に歩きましょう」と促す
⇒歩行能力を考えながら、自分の力で歩く機会を増やすことで歩行能力の維持・向上につながる
×:「危ないから座っててください」とすべての家事をサポートする
⇒役割が全てなくなると「自分は何もできない」と感じ自信喪失につながる
〇:「座りながらテーブルを拭いてみませんか?」と声をかける
⇒できる範囲で家事を手伝ってもらい、「役に立っている」実感を得てもらう
高齢者の方の能力を把握し、できること・サポートが必要なことを知ることが大切です。

自立支援を行うことで、身体機能の維持・向上や精神的な安定につながり、利用者の豊かな生活にもつながっていくのね。

安全に配慮しながら、できることを増やしていくことで、高齢者の方の自信にもつながるんだ。
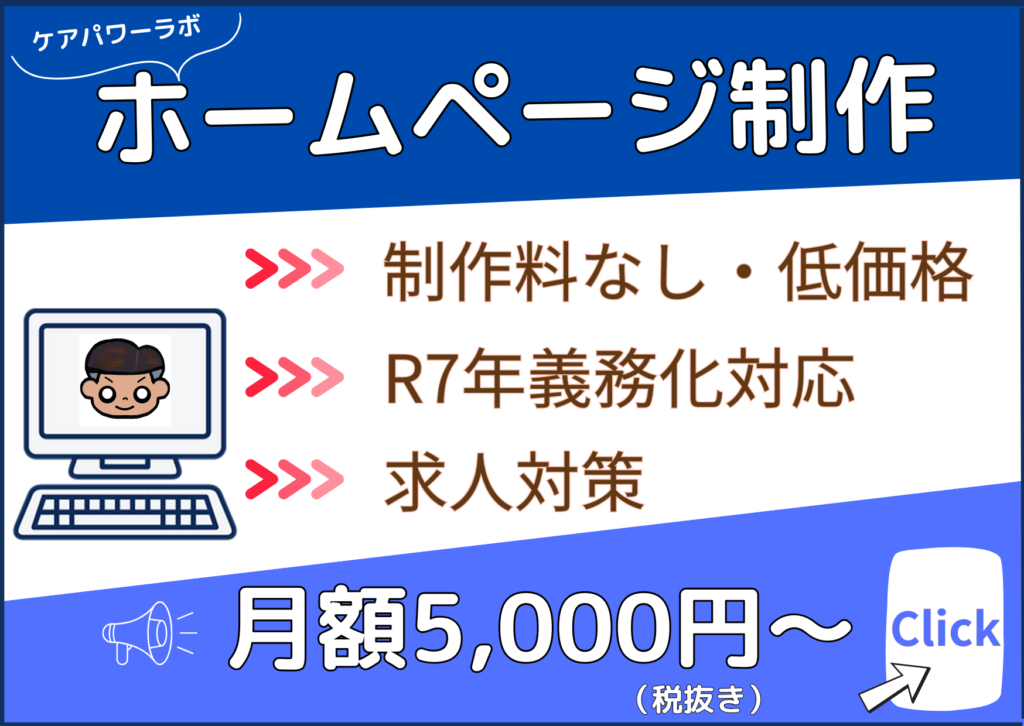
高齢者の心理におけるポイント
高齢になると、身体の変化や生活環境の変化により、さまざまな心理的課題を抱えます。
・孤独感
・不安
・役に立ててないと感じる気持ち
は多くの高齢者が直面します。
これらの課題に適切な尊厳を守るケアを行い、対応することが大切です。
高齢者が感じやすい心理的課題と対応方法

高齢者が感じやすい心理的課題と対応方法について3つ確認していきましょう。
孤独感
<心理的課題>
・配偶者を亡くしたり、家族と過ごす時間が減ったりすることで、寂しくなる。
・外出が減り、社会と接する機会が減少し孤独感が強くなる。
<対応方法>
・訪問時に会話の時間を意識的に増やし、寂しさを払拭する。
・ケアマネ(サ責)に相談し、歩く事が可能であれば、買い物などヘルパーと一緒に行く計画書をつくり、スーパーの店員など社会とのつながりを持てる第一歩にしていく。
不安
<心理的課題>
・老化に対しての不安(転倒など)
<対応方法>
・ケアマネ(サ責)に相談し、介護ベッドや手すりなどの存在があることを伝えてもらい、不安を取り除く。
役にたててないと感じる気持ち
<心理的課題>
・「何もできなくなった」「誰の役に立てない」という思いから自信を失う。
<対応方法>
・その人のできる事(簡単な家事など)を探し、できる作業をお願いする。役割を持ってもらうことで自信の回復につなげる。

なんでもできた時の自分と比べて喪失感が大きいのかも・・・。

ちょっとした気遣いが、不安をなくして安心を与えてあげられるんだね

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。
まとめ
・尊厳を守ることで高齢者の心理的安定につながる
・自立支援をすることで、できることが増え、QOL(生活の質)が向上する
・「介護される人」ではなく「その人らしい生活が送れる人」となるようケアをする
尊厳を守るケアを実践することで、高齢者は「大切にされている」「自分の意思が尊重されている」と感じ、心理的にも安定します。
また、自立支援によって「できることが増える」「役に立っていると実感できる」ことで生き生きとした生活につながります。
介護の現場でヘルパーの行動は利用者の自立と尊厳を支え、その人生をより豊かにする力をもっています。日々の小さな配慮や声掛けが利用者に安心感や希望を与えることにつながります。
忙しい中でも、「その人らしい生活を支えるケア」を意識し行動する事で、利用者の笑顔や感謝に触れる習慣が増えるはずです。
利用者、そしてヘルパーもより良い毎日を送れるよう、心のこもったケアを続けていきましょう。
研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン
アンケートの実施
記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。
ブログの質の向上に役立てさせていただきます。
アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

【参考資料】
厚労省 介護保険制度の概要 介護保険とは
厚労省 認知症基本法概要
厚労省 2015年高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~
地方独立行政法人東京と健康長寿医療センター「本人にとってよりよい暮らしガイド一足先に認知症になった私たちからあなたへ」
高齢期作業療法学 第2版 医学書院 矢谷令子

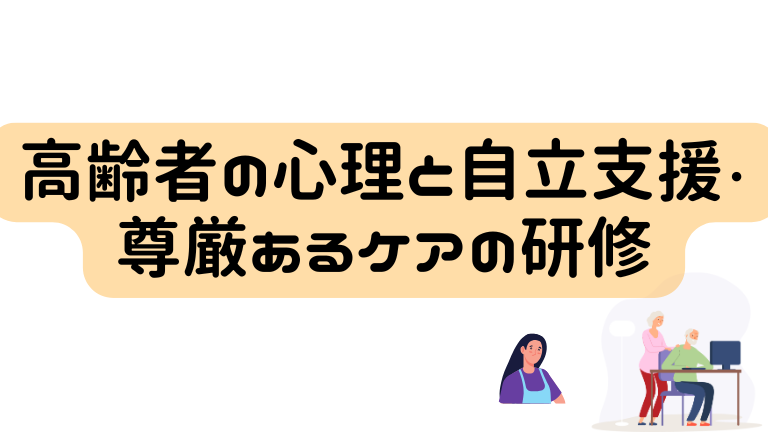

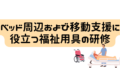
×:黙って一口ずつ食べさせる
⇒本人のペースを無視すると「食べさせられている」と感じてしまう
〇:食事のペースや好みを確認しながら介助する
⇒「一口はこの量で大丈夫ですか?」「どのおかずから食べますか?」など声掛けをし、本人のペースや食の好みに配慮する