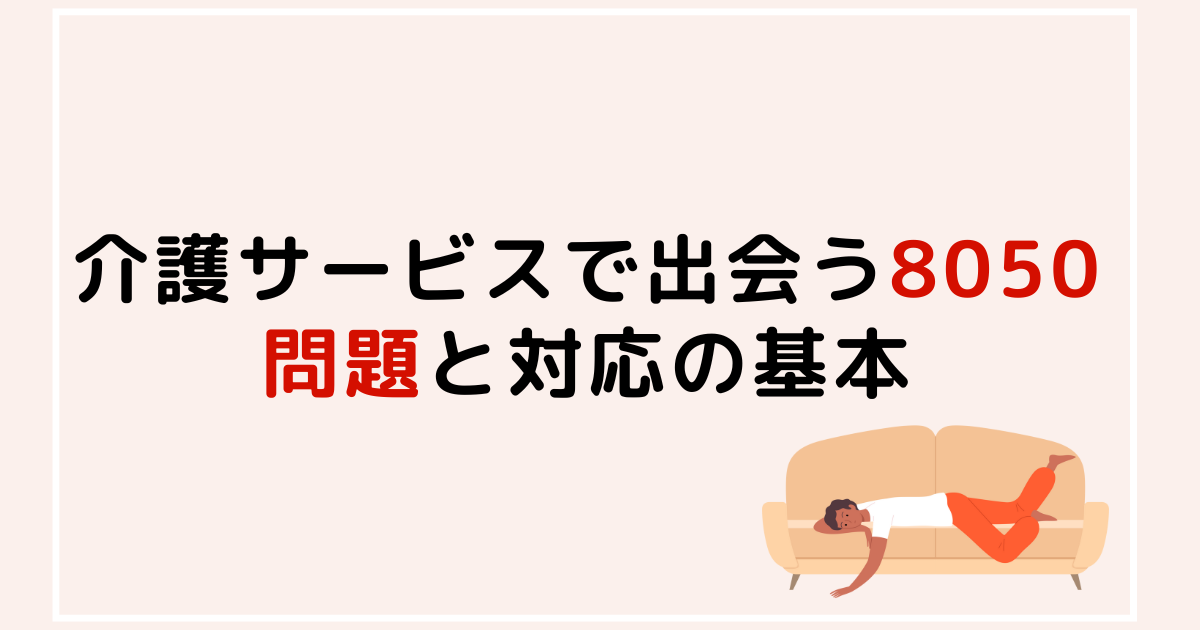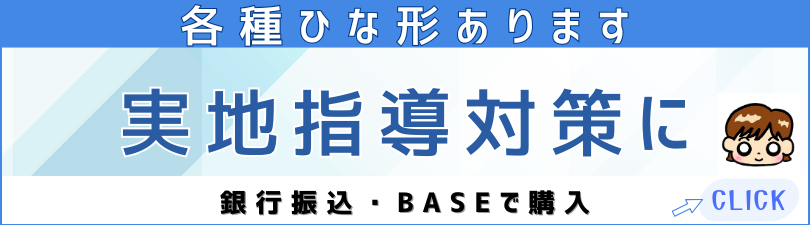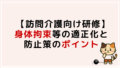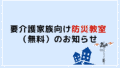※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください
はじめに
私たちは、利用者宅で「これはどうしたらいいのだろう…」と迷う場面が本当に多い仕事です。
🔻例えば、サービス中にこんな経験はないでしょうか??
- 冷蔵庫を開けてみたら、ほとんど何も入っていない。
- 利用者が「息子が働かないからお金が足りないのよ」と訴えてくる。
- 介護度が上がっているのに「これ以上サービスを増やしたら生活できなくなる」と断られた。
このような場合、親子共に支援が必要なケースとして、
8050問題の要素を含んでいるかもしれません。
以前は「ひきこもり」というと若い人の問題だと考えられがちでしたが、今では年齢層が広がり、親も子も高齢化しています。
8050問題とは

「80代の親」と「50代の子ども」が同居していて、子どもが長期間ひきこもりや無職の状態にある家庭で、親の介護や生活支援を担う人がいないまま、親子ともに孤立・困窮していく状況を指します。
親の年金や貯金を頼りに生活しているため、親が高齢で要介護になると家計も介護も一気に苦しくなります。
この問題は、単なる「親子の問題」ではなく、社会全体が抱える課題です。
「怠けている」ではなく「支援が届いていない」
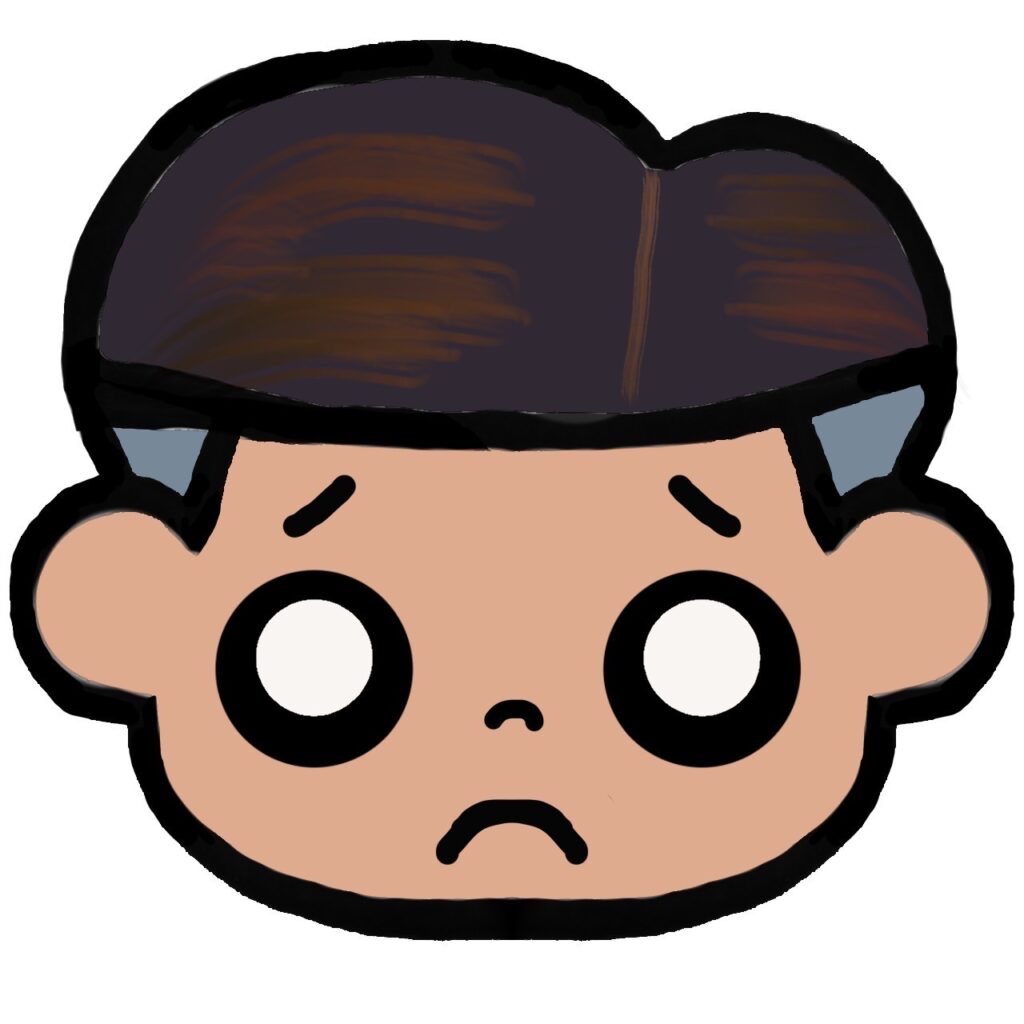
「働かないのは本人の怠け」と思われがちだけど、実際にはいくつもの要因が重なっているんだ。
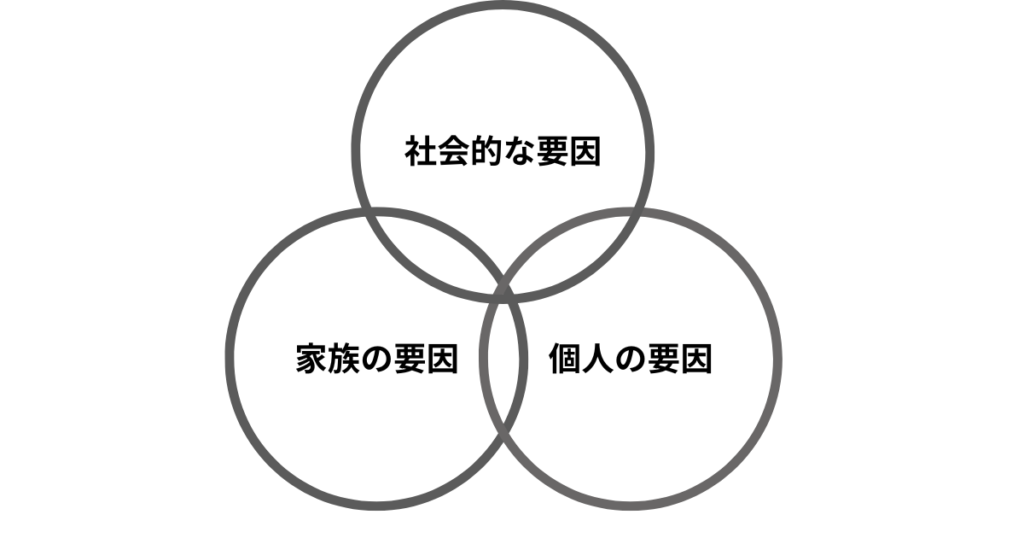
社会的な要因
- 就職氷河期世代(概ね40歳〜55歳)で、若いころ正社員になれず非正規社員・アルバイトだった。
- 学校や職場での競争が激しく、挫折経験を抱えている。
- 家に長い時間こもることで、仕事に必要なスキルが身に付かない。
✅就職氷河期世代:おおむね40歳から55歳の人を指し、バブル崩壊後の厳しい雇用環境下で就職活動を経験した世代。
家族の要因
- 親が生活費を出し続けることで自立できなくなった。
- 世間体や、子どもに「怠けている」というレッテルを貼りたくないという気持ちから、外部の支援をためらう。
個人の要因
- 職場での人間関係トラブル・リストラで立ち直れない
- うつ病などの精神的な問題がある。
- 発達障害などで環境に適応できない。
つまり、本人だけの問題ではなく、社会や家庭の事情も重なり合っている状態です。
ひきこもりの方は、社会への罪悪感やプライドから、助けを求めること自体ができない場合も多くあります。そのため「支援が届いていない」状況にあると理解することが重要です。
8050問題は実際に何が問題となるのか??

長期化するひきこもりで負のループに…
一度社会から離れると、なかなか元の生活に戻ることが難しいのが今の社会です。
特に中高年になってからの再就職は、年齢やブランクがあることでさらにハードルが高くなり、ひきこもりが長期化すると、外に出ることや人と関わること自体が大きなハードルになります。
また、40代や50代で職歴が途切れていると、再就職の場は限られ、選べる仕事も少なくなります。
仕事に就けないことで、親の年金に依存してしまうといった負のループに…。
経済的困窮
子が無職で収入が不安定なため、親の年金が家計の主な収入源になります。
年金だけでは生活費・医療費・介護費をまかなえず、慢性的な赤字家計に陥るケースが多いです。
社会的孤立
ひきこもりの問題は、本人だけでなく家族も深く関わっており、特に親が「恥」と思ってしまう事から状況を隠してしまうケースが多い事もあります。
親子ともに家に閉じこもりがちになり、外とのつながりがなくなる。恥や遠慮から支援を求めづらく、親子の依存関係が強まって、ますます社会から孤立していきます。
周囲に相談せず、支援機関との接点を持たないまま年月が経過することで、問題が深刻化し、支援につながりにくくなる傾向があります。
✅長期間にわたり親子だけで生活していると、介護疲れや感情の衝突が積み重なり、思わぬトラブルや虐待につながることもあります。
➔ 【訪問介護の高齢者虐待防止の研修】ケアパワーラボ
問題にならないケースもある
「8050」って言葉を聞くと、すぐに何とかしなきゃいけないと捉えがちです。
しかし、実は全部がそうではありません。
お金に余裕があって、働いていない子供がいても、家族でうまくやっているところもあります。
ですので、「8050だから問題」と決めつけるのも危険です。
大切なのは、その人や家族がどんな暮らしをしているか、何に困っているかを見極めること。
必要なときに、そっと支えられるように見守る姿勢こそが本質です。
問題にならないケース(リスクが小さい例)
• 親と子の間で良好なコミュニケーションが取れている。
• 社会や支援機関とのつながりがある。
• 親子ともに経済的に自立している(資産があるなど)
今は安定していると見える家庭でも、ちょっとした事で状況は変わりますので、常に気にかけておく必要があります。
8050問題を見かけたらどうする??
私たちは、家庭の様子を日常的に見ているからこそ、いち早く異変に気づける貴重な存在です。
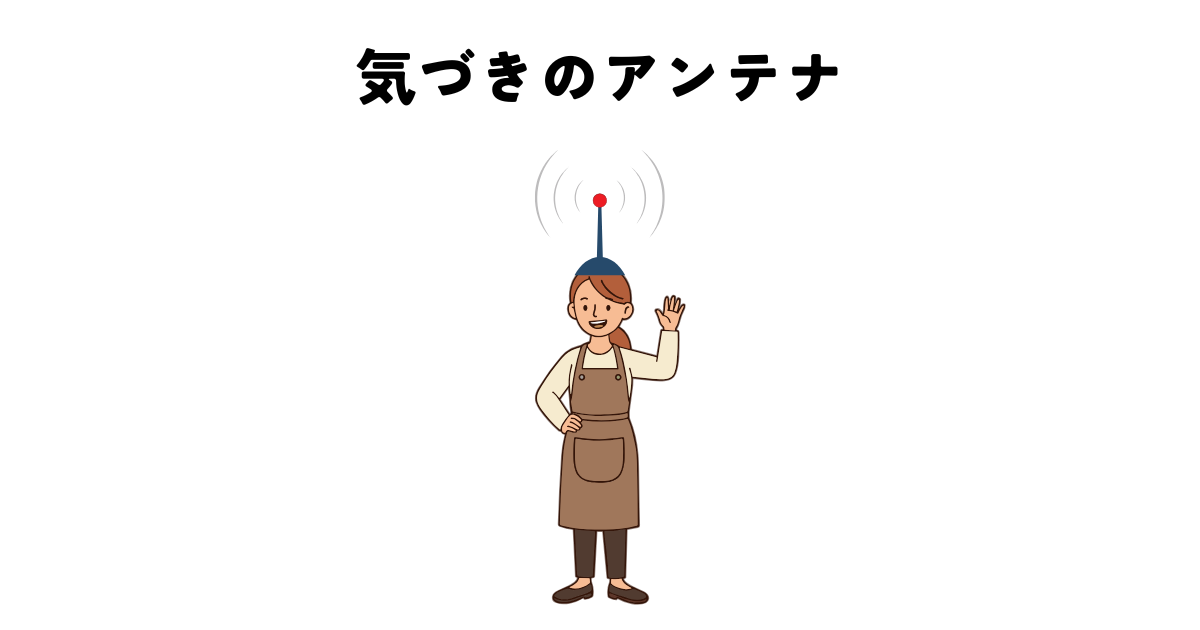
役割としては、「気づきのアンテナ」を持って困りごとを早期に発見し、適切な支援機関に「つなぐ」ことです。

具体的な支援を行うのは専門機関だけど、そのきっかけを作るのは私たちの日々の働きかけね。
「気づき」と「つなぐ」
🔻訪問サービスでは、利用者本人だけでなく家庭の様子も目にします。
- 気づく:冷蔵庫、部屋の様子、光熱費の督促状など生活のサインを拾う
- 報告する:ケアマネやサービス提供責任者に「生活費が原因でサービスを抑えている」と伝える
- つなぐ:ケアマネを通じて包括支援センターや役所につなぐ
直接支援制度を勧めない理由
利用者や家族にどんな制度を勧めるかの判断は、専門職や自治体が行います。
「この制度を使ったほうがいいですよ」と勧めるのは責任が持てず、家族の信頼を失ってしまう可能性があります。
実際の事例
私が担当した利用者の実際のケースを紹介します。
ケース:山田さん親子(仮名)
山田さん(80歳・要介護2)は年金8万円で息子と二人暮らし。息子(52歳・無職)の生活費も山田さんが負担。
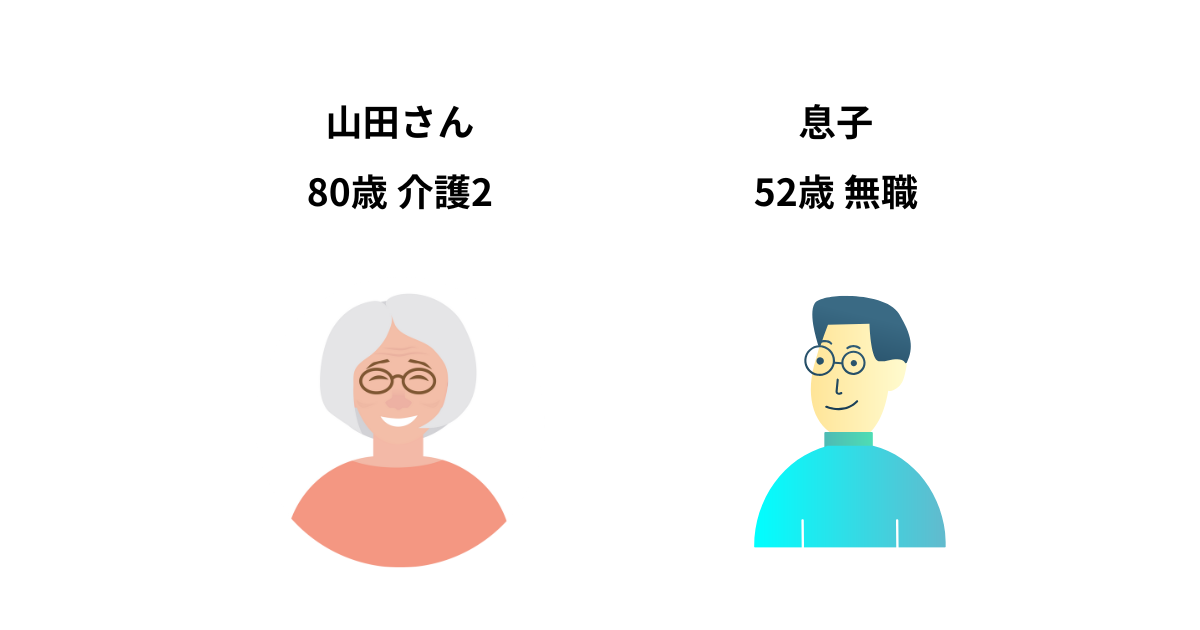
山田さんは、介護サービスを増やしたい気持ちはありましたが、
「これ以上は生活できないから」
と利用を抑えていました。
ヘルパーからは以前より、
「生活費の不足でサービスを削っている」
「冷蔵庫が空に近い状態」
といった報告を受けており、
私(ケアマネ)も支援が必要な状況と判断していました。
しかし当時は本人が
「まだ大丈夫」
と話しており、支援機関への同意が得られませんでした。
ところが、山田さんが肺炎で入院。
ほとんど所持金がなく、医療相談員から
「このままでは入院生活も、その後の生活も成り立たない」
と連絡が入りました。
そこで私(ケアマネ)は、これまでの生活状況とヘルパーからの情報を整理し、地域包括支援センターに報告。
その結果、息子の生活も含めた支援が必要と判断され、
「生活困窮者自立支援制度」
へとつながり、家計相談や一時的な貸付、就労準備支援が開始されました。
日々の関わりの中で、ヘルパーが「気づき」のアンテナを持ち、共有してくださったことで、支援の方向性を見つける大きなきっかけとなりました。
気づくためのアンテナを持ちましょう。

🔻気づくためのアンテナ
- 冷蔵庫の中が極端に少ない。
- サービスを追加したほうがいいのに拒否がある。
- 光熱費の滞納通知がある。
- 極端に節約している。
- ゴミがたまって生活が乱れている。
こうしたサインを見たら「何かあるかもしれない」と思うことが大切です。

次は、制度と窓口について簡単に理解しておこう。
生活困窮者支援制度
この制度は、一言でいえば
生活保護になる前の段階で支援する仕組みです。
病気や失業、家庭の不和などで生活が立ち行かなくなった人に対して、仕事・お金・住まいなどの相談をまとめて受ける制度です。
🔻主な内容は以下の通りです。
- 自立相談支援事業:生活全体の相談窓口。支援員が課題を整理し、一緒にプランを立てます。
- 住居確保給付金:家賃が払えない人に、一定期間家賃を補助。
- 家計改善支援:家計簿の見直しや債務整理の相談。
- 就労準備支援:働く前段階の生活訓練や社会参加支援。
この制度の窓口は、市区町村の「自立相談支援機関」(多くは社会福祉協議会が担当)です。
ひきこもり地域支援センター
こちらは、
ひきこもり本人や家族の相談を受ける“都道府県設置の専門窓口”です。
保健師・心理士・ソーシャルワーカー等が常駐し、必要に応じて医療機関や地域の支援機関と連携します。
簡単に言うと、
ひきこもり支援の「ハブ」となる機関です。
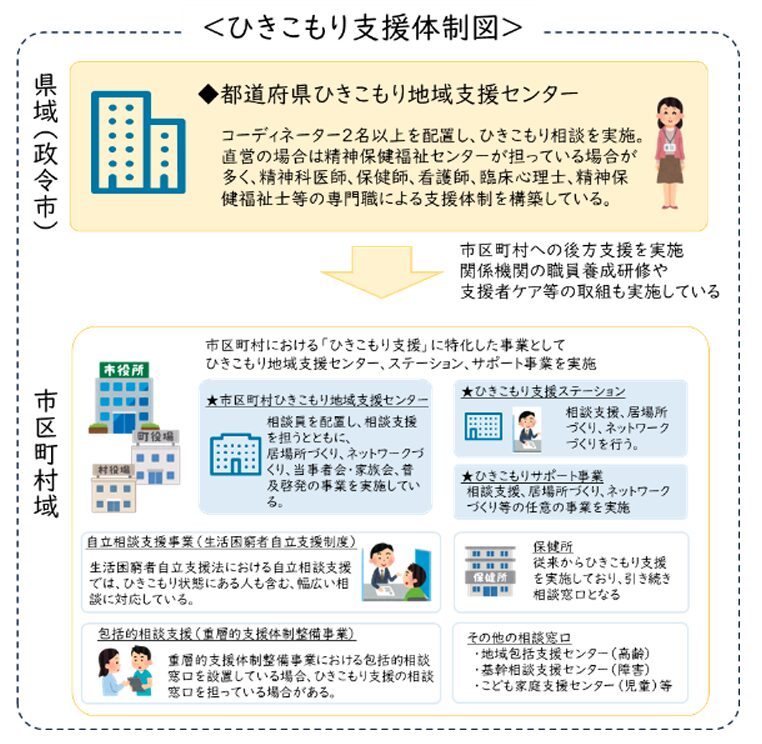
画像引用:厚労省 ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤 001471237.pdf
8050問題に気づいたときの流れ
🔻流れは次の通り。
- step1まずはサービス提供責任者・ケアマネに状況を報告

- step2ケアマネから地域包括支援センターに相談

- step3地域包括支援センターが相談先を判断
状況に応じて最適な機関へつなぎます。
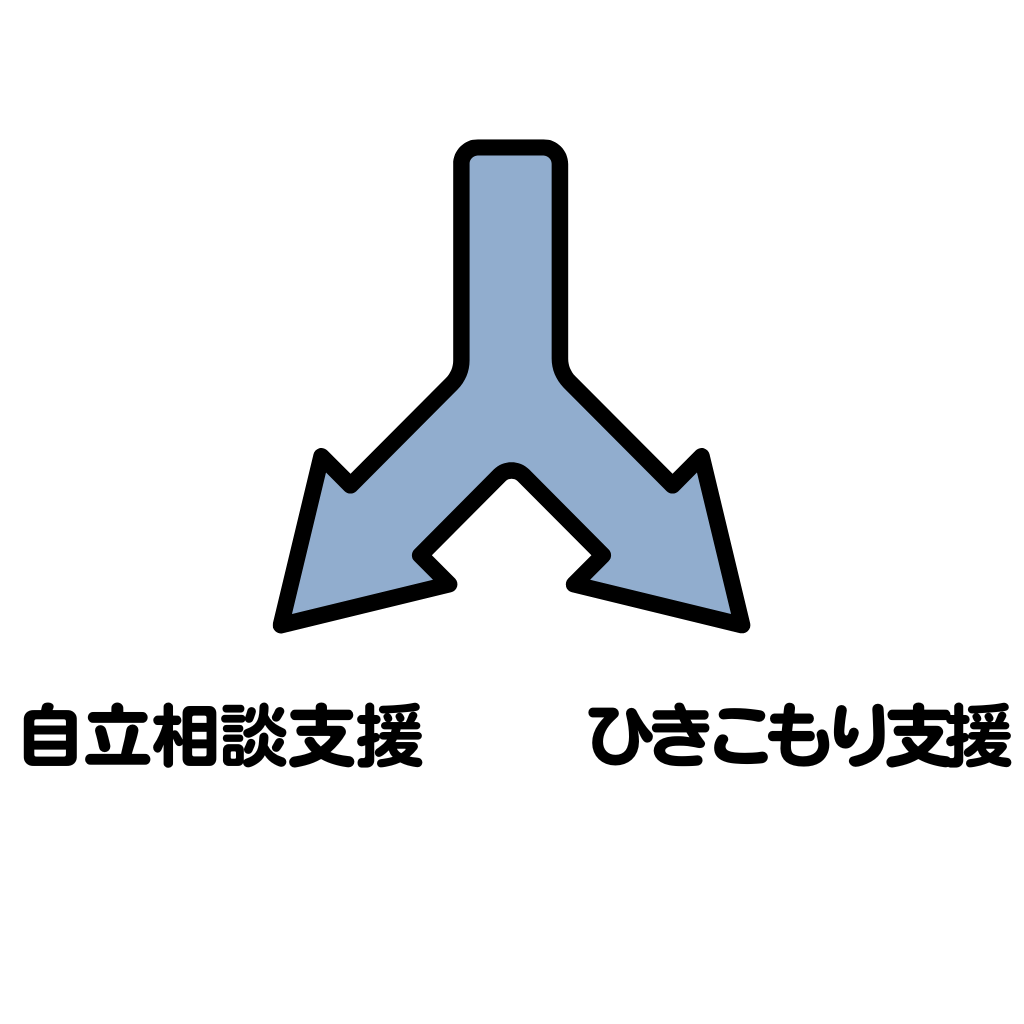
🔻経済的な困りごと
→ 自立相談支援機関
🔻社会的孤立
→ ひきこもり地域支援センターなど
このように、ヘルパーが最初に“気づいて、ケアマネにつなぐ”ことで、世帯全体の支援へ広げることができます。
✅地域包括ケアの考え方を知ることで、8050世帯への支援の幅は大きく広がります。
➔ 訪問介護の地域包括ケアシステムの理解研修 ケアパワーラボ
相談先の一覧
- 地域包括支援センター:介護や生活全般の相談窓口
- 生活困窮者自立支援機関:就労・家計・住居の支援
- ひきこもり地域支援センター:長期ひきこもりの相談
- 精神保健福祉センター:心の問題や精神疾患の相談
- 市区町村の福祉課・生活支援課:生活保護や重層的支援体制の窓口など
※地域によって名称は異なります。
✅利用者やご家族からのしつこい依頼や、「少しくらいやってくれてもいいでしょ?」という圧力に悩んだことがある方へ。
どう対応すればいいのか──
➡ 利用者・家族からのカスタマーハラスメントへの対応と防止策|ケアパワーラボ
▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」
→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/
まとめ
8050問題は、単なる家族の問題ではなく、社会全体で考えていくべき課題です。
私たちは日々の訪問を通じて、困っているご家庭の「気づき」のきっかけを作り、適切な支援機関に「つなぐ」という、かけがえのない役割を担っています。
「気づく → 伝える → つなぐ」
この流れを意識するだけで、家庭が孤立のまま崩れてしまうのを防ぐ可能性が高まります。
地域で暮らす私たちみんなが、互いに支え合い、誰もが安心して暮らせる社会を目指していきましょう。
• 厚生労働省 ひきこもり支援に関する取組:
• ひきこもりVOICE STATION:

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン
本資料は、介護の現場での共有・活用を目的として作成しています。 以下のようなご利用はご自由にどうぞ:
・印刷して使用
・職場内での回覧・配布
・個人での保存・参照
ご遠慮いただきたいご利用
以下の用途でのご使用はお控えください:
・無断転載(Webサイト・SNS等への投稿など)
・無断での再配布・再編集(PDF配布、内容の加工などを含む)
・商用利用(有料教材・商品の一部としての使用など)
文章・図表などの無断引用(出典・文脈の明示がないままの一部使用など)
外部でのご紹介・引用について
外部メディア・資料・SNS等で当資料の一部を引用・掲載される場合は、 必ず以下のように出典を明記してください:
※文脈を歪める形での引用や、誤解を招く編集はご遠慮ください。 不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください: info@care-power-lab.com
★リンク・ご紹介は大歓迎です!
皆さまのつながりが、介護現場の力になります。
本記事はPDFとして印刷できます
【訪問スタッフ向け】
現場でそのまま使える「介護サービスで出会う8050問題と対応の基本」を、わかりやすく整理しました。
✅介護サービスで出会う8050問題と対応の基本・印刷用PDFはこちら
整えたレイアウトでそのまま印刷OK
研修・ミーティング・配布用
アンケートの実施
記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。
ブログの質の向上に役立てさせていただきます。
アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩